後期高齢者医療制度
概要
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が保険者となり、市町村が協力して運営しています。
75歳以上のかた(65歳以上で一定の障害があると認定を受けたかたは、本人の希望により)は、これまでの国民健康保険、健康保険組合や共済組合などの被用者保険(被扶養者であったかたを含む)の資格はなくなり、後期高齢者医療制度に加入することになります。
運営のしくみ
運営主体
制度の運営は、県内全ての市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が行います。
広域連合が行うこと
「埼玉県後期高齢者医療広域連合」では、保険料の決定、資格の管理、医療費の支給などの事務・財政運営を行います。
市が行うこと
資格確認書などの引渡し、加入などの申請や届出の受付、保険料の徴収などの窓口業務を担当します。
被保険者(対象者)
被保険者
- 75歳以上のかた
- 65歳以上で一定の障害があると認定を受けたかた
資格確認書
1人に1枚、後期高齢者医療資格確認書が交付されます。
保険料
保険料の決め方 (保険料は、埼玉県後期高齢者医療広域連合で決定されます)
保険料は個人単位で計算されます。
保険料=均等割+所得割負担割合について
所得による負担割合
| 区分 | 該当要件 | 窓口での負担割合 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 |
住民税の課税標準額が145万円以上の被保険者のかたが、1人でも世帯にいる場合 |
3割 |
| 一般 |
世帯にいるすべての被保険者のかたの住民税の課税標準額が、145万円未満の場合 |
1割・2割 |
| 低所得2 | 世帯主および世帯全員が住民税非課税である場合 | 1割 |
| 低所得1 |
世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、各所得(収入-必要経費など)が0円であり、公的年金収入が80万円以下の場合 |
1割 |
毎年8月に再判定を行い、新しい資格確認書あるいは資格情報のお知らせを郵送します。
基準収入額適用申請について
現役並み所得者(3割負担)のうち下記に当てはまるかたは、申請して認められると、負担割合が変更となります。なお、申請月の翌月から適用されます。
2割・1割負担になる場合
1.世帯の中に被保険者が1人
→前年の収入が383万円未満のかた
→前年の収入が383万円以上で、同一世帯の70歳から74歳のかたを含めた収入が520万円未満のかた
2.世帯の中に被保険者が2人以上
→前年の被保険者の合計収入が520万円未満のかた
1か月の自己負担限度額(平成30年8月診療分から)
| 区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯合算) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (注 140,100円) | |
| 現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (注 93,000円) | |
| 現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (注 44,400円) | |
| 一般 | 18,000円 (年間144,000円上限) | 57,600円 (注 44,400円) |
| 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
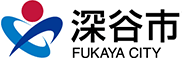




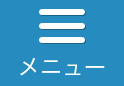

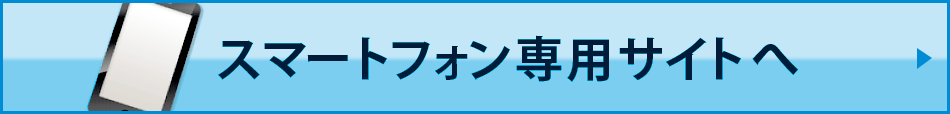
更新日:2024年12月02日