誠之堂のステンドグラス
大広間
 |
 |
 |
 |

|
 |
誠之堂大広間の暖炉脇の窓には、6面のステンドグラスが配され、大きな見所となっています。
中国風の珍しい題材ですが、これは設計者の田辺によれば、中国漢代の「画像石」の図柄を模したものです。庶民貴人と侍者、それを饗応する歌舞奏者や厨房の人物たちの像は、栄一を貴人に見立て喜寿を祝う情景と考えられています。
図案は、田辺の部下であった森谷延雄(明治26年-昭和2年、1893-1927)によることがわかっています。また、記録はありませんが、点付けハンダの技法等から、製作は、宇野澤組ステンドグラス製作所によると推定されています。
場面は、右から順に取り上げています。

第1面
第1面と第2面は、貴人とその臣下たちを描いた場面です。
第1面では、中央に貴人が台に座り、両側に侍者を従えています。この台は、「榻(しじ)」と呼ばれるもので、この上に座れるのは、帝や貴人だけです。
人物の衣装は、「袍衣(ほうい)」と呼ばれる広袖の服で、漢時代から始まった衣服形態です。
貴人は、片手を挙げ、何か指示をしているのか、左の侍者と会話をしているようです。

第2面
貴人の左には、3人の臣下が列席しています。
みな左手の第3面で行われてる舞楽を見物しているのでしょう。
右にあるのは、瓶や食器で宴会に使われるものでしょうか。左には果実のなった木も生けられています。
上に飛んでいるのは、ツバメのようで、この饗宴は、屋外で行われているのかもしれません。

第3面
第3面と第4面は、貴人を饗するための楽器演奏と雑技を行っている場面です。
見える楽器は、右は笙、左は簫の一種でしょうか。小鼓の仲間かもしれません。
中央の人物は、倒立技を演じています。雑技の倒立技は、漢の時代に著しい発展をしたそうです。

第4面
第3面に続き、楽器演奏と雑技を行っている場面です。
右では、筒太鼓を叩いているようです。
中央では、「弄丸鈴」という、複数の玉を投げる手技の雑技を行っています。
左で踊る女性は、大きく反って、腕は極端に長く引き伸ばされた姿で描かれています。流れるような動きが強調された興味深いデザインです。

第5面
第5面と第6面は、「庖厨図」と呼ばれる図案で、宴会のための料理の風景を表わしています。
右では、魚をさばいています。また、左では、かまどに火を起こして、大鍋で何かを煮炊きしています。
魚の模様や顔の目など、細かい部分は、薄く切った鉛をガラスの表面に貼る「帯貼り技法」と呼ばれる方法で描かれています。

第6面
左の人物は、何かだんごのようなものを丸めています。
右の2人の足元にある黄色いものが、だんごになるのでしょうか。
当時の主食は、黍(きび)だったそうです。この黄色い穀物も黍で、2人は、これを蒸したり、ひいて粉にしているところかもしれません。
化粧の間
 |
 |
化粧の間の扉にも、鳳凰と龍のステンドグラスが取り付けられています。玄関から入るとすぐに目を引きます。
ひし形の格子に中央上部にシンボルとして図柄や家紋などを配する手法は、ヨーロッパの伝統的なステンドグラスに散見されます。
デザインは誰によるものかは不明ですが、製作は、大広間のものと同じく宇野澤組ステンドグラス製作所によると推定されています。

鳳凰
鳳凰も龍も、ともに中国風の意匠ですが、中国では、龍は「男子(皇帝)」鳳凰は「女子(皇后)」のシンボルだそうです。ともにめでたい意匠として採用されたことは、間違いないところでしょう。
この鳳凰は、渋沢栄一の当時夫人だった、兼子夫人を表わしているのかもしれません。
輪郭のハンダは盛り上げて付けられ、立体感を与える技法が用いられています。

龍
龍は「男子(皇帝)」のシンボルです。それに倣えば栄一を指したものと考えられます。
また、栄一と龍といえば、渋沢邸の書生たちが結成した「竜門社」が連想されます。「竜門社」が栄一の80歳を祝して贈った「青淵文庫」の閲覧室の欄間のステンドグラスにも、名前に因んだ龍のステンドグラスが見られます。
参考文献
清水建設株式会社著「誠之堂ステンドグラス調査報告書」(平成13年、深谷市発行)
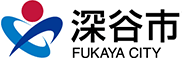




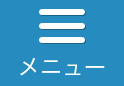

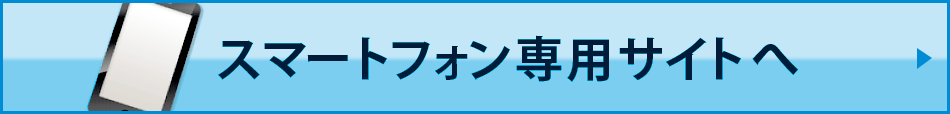
更新日:2025年11月19日