|
深谷市民の生活安定・向上のため、さらには少子高齢化という難題を抱えながら、日々市政の運営に全力で取り組まれている小島市長に心より敬意を表します。
また、私ども「連合埼玉」熊谷・深谷・寄居地域協議会の活動に対して、日頃より深い連帯ならびにご理解とご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。
さて、私たち「連合埼玉」熊谷・深谷・寄居地域協議会では、「安全・安心な地域社会」の実現を目指す取り組みとして、市政への政策制度改善要請項目を以下のようにまとめました。本要請は、地域に働く労働者の生活の向上から、地域社会の活性化をはかり、住みよい「まちづくり」に繋げていく。そこからさらに安心安全な地域社会の確立に向けた政策制度事項であります。
また、これまでの要請の中ですでに回答を頂いている項目もございますが、進捗状況などの再確認を踏まえて記載させていただきましたことご理解をお願いいたします。
つきましては、本要請を深谷市の行政に十分反映され、更に市政が発展、拡充されることを期待し要請を致します。
要請項目 8分野 32項目(連合埼玉統一要請)
市町村統一政策・制度要請(8分野32項目)について
総合経済・産業政策
1.「公契約条例」制定について
すべての産業を対象に、公契約のもとで働くすべての人の雇用・労働条件を守り、住民がより良い公共サービスを受けられるよう、ILO第94号条約型の「公契約条例」を制定すること。
<要請の根拠>
埼玉県内では、すでに公契約条例を制定した草加市・越谷市があり、その必要性や重要性については理解が進んでいる。また、上尾市・富士見市などでは、公契約に係る適正な履行の確保および労働環境の整備に配慮した調達の推進をはかるために「公契約に係る労働環境の確認に関する要綱」として定めており、公契約の際に必要な手続きを定め公契約の適正化を促している。
特に、賃金条項においては、草加市・越谷市で公契約条例に盛り込まれており、上尾市や富士見市では、労働環境の確認に関する要綱の中で、支払賃金の確認をおこなう要綱となっている。また、現状の原材料高、エネルギー高などによる物価上昇の中で、公契約事業に携わる労働者の賃金においても、賃金を引き上げる必要がある。
公契約条例は、本来、事業者・労働者・地域住民そして行政と、全ての関係者にとってプラスとなりうるものであり、また条例(労働条項型)の制定により、「公契約に従事する労働者などの適正な賃金・報酬の確保」「入札におけるダンピング受注防止、適切な落札率・発注額への改善」「地域事業者の育成と人手の確保」「地域経済・社会の活性化と好循環」などの効果も期待される。
そのような中、東京都内では、ILO第94号条約型を制定する自治体の動きが加速化してきている。しかし、これまで条例制定が進まなかった理由として、「行政が事務負担の増加をいやがっている」「事業主が、受注金額が上がらずに労務費や条例に関わる事務負担増を懸念する」などの声が挙げられていた。
埼玉県および各市町村においては、公契約をおこなう発注者という立場から、税金の公正な支出と公共サービスの質を確保し、公契約事業に携わる労働者の労働条件ならびに賃金水準も確保するためにも、「賃金条項」を盛り込んだILO第94号条約型の「公契約条例」を制定する必要がある。
【回答】
公契約条例の制定に関しては、国は、批准の前提となる国内法令の整備が困難であるとして、ILO第94号条約の批准は行っておりません。また、現行の労働関係法令において、賃金その他の労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものとされておりますことから、現状においては、市として公契約条例の制定は考えておりませんが、引き続き、国・県及び近隣自治体等の動向把握に努めてまいります。
2.中心市街地・地域商店街活性化の取り組み推進について
各地域の実情をふまえながら、地域住民が参画するまちづくりを支援する「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」を活用した「地域のまちづくり」の取り組みを推進すること。
<要請の根拠>
中心市街地は、商業、業務、居住などの都市機能が集積し、長い歴史の中で文化、伝統をはぐくみ、各種機能を培ってきた。しかしながら、病院や学校、市町村役所などの公共公益施設の郊外移転等都市機能の拡散、モータリゼーションの進展、流通構造の変化などによる大規模集客施設の郊外立地、居住人口の減少等中心市街地のコミュニティとしての魅力低下、中心市街地の商業地区が顧客・住民ニーズに十分対応できていないことなどにより、中心市街地の衰退が進みつつある。
中心市街地活性化基本計画(※1)の認定実績は、全国で155団体(151市4町)、累計で283計画(令和6年4月現在)であり、埼玉県内では、川越市(2回)、蕨市、志木市、寄居町だけである。また、特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(※2)認定は全国で19件にとどまっており、県内では川越市のみである。(令和6年4月現在)
このような県内の状況では、行政の支援が有効に活用されているとは言い難く、地域の実情や実例をふまえた検討やフォローアップが必要である。さらに、地域商店街活性化のために、地域住民のニーズに沿った新たな需要を創出する施設などの導入や最適なテナントミックスの実現に向けた地域商業機能複合化事業、あるいは外部人材活用・地域人材育成事業の活性化が必要であり、支援の強化が求められている。
【参考情報】
※1)中心市街地活性化基本計画は、中心市街地の活性化に関する法律に基づき、市町村が商工会議所、民間事業者、地域住民などによる中心市街地活性化協議会と連携して作成する。国の認定を受けた計画は、国の支援を受けられる。
※2)特定民間中心市街地経済活力向上事業計画は、中心市街地活性化基本計画に基き、
1.意欲的な目標を掲げ(年間来訪者数が中心市街地の居住人口の4倍以上など)
2.中心市街地の経済活力を向上させる波及効果があり
3.地元からの強いコミットメントがある民間商業施設整備プロジェクトに対して、経済産業大臣が認定した場合、税制優遇・低利融資等の支援が実施される。
【回答】
本市では、平成11年に中心市街地活性化基本計画を策定し、平成14年に深谷商工会議所をTMO認定して中心市街地活性化の事業を進めております。
なお、本計画は国の認定制度の開始前に策定されたため、国の認定は受けておりません。
商店街の活性化につきましては、令和元年度に県の「NEXT商店街」事業を活用して外部の専門家と共に、商店街内外の人材を巻き込みながら地域資源探しや誘客イベントの開催、空き店舗活用事業を実施しており、引き続き「地域のまちづくり」の取組を推進してまいります。
3.自治体におけるDX推進について
地方自治体において、マイナンバーカードの取得促進やAI、ローカル5Gなどのデジタル技術の積極的な活用により、住民の利便性向上や行政の効率化を図ること。
また、デジタル・デバイド(インターネットやパソコンなどの情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差)への対策を強化すること。
<要請の根拠>
2020年12月、政府は「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」を策定し、目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会~誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化~」を示している。
また、このビジョンの実現のためには、住民に身近な行政を担う自治体、とりわけ市区町村の役割は極めて重要として、「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」を策定し、自治体が重点的に取り組むべき事項や政府の支援策をまとめており、確実な実施が求められている。
さらには、デジタル化を進めるにあたっては、年齢、障害の有無、性別、国籍、経済的な理由などにかかわらず、誰も取り残さないかたちで、全ての国民にデジタル化の恩恵を広く行き渡らせる環境の整備に取り組むことが必要と考える。
そのためにも、デジタル機器の講座開催、デジタル活用を教えるための人材育成、デジタル機器の購入などの補助、協力団体への支援、自治体HPにおけるアクセシビリティ改善などが必要と考える。
【回答】
マイナンバーカードの取得促進に関する取組につきまして、本市ではマイナンバーカード専用のコールセンターを設置しており、カードの申請・受け取り方法の案内をはじめ、交付予約の受付やその他様々な問い合わせに対応し、市民の疑問や不安解消に役立てております。
また、介護施設や障害者施設等へ入居中で、自身でのカード申請が難しいと思われる方に対し、市職員が各施設へ直接赴き申請手続きのお手伝いをする、団体出張申請受付サポートを展開しております。今年度は、現在までに6施設(7回)実施しており、実施日程調整中の施設を含め、数多くの施設より問い合わせをいただいております。
さらに本市では、昨年3月から、住民票の写しなどコンビニエンスストアで取得できる証明書コンビニ交付サービスの手数料を、窓口での交付と比較して50円の値下げを実施し、併せてコンビニ交付の操作マニュアルの小冊子を作成し毎戸配布するなど、マイナンバーカードの利便性を周知しております。
この様な取組により、マイナンバーカードの取得促進に努めております。
本市ではデジタル技術の活用によって市の課題解決を図ることを目的として、令和4年3月に深谷市デジタル化推進計画を策定し、各種ICTツールを導入するなど、市民の利便性向上及び業務の効率化を図っており、今後も新技術の動向に注視するとともに、導入について研究してまいります。
また、デジタルデバイド対策として、デジタル端末等に不慣れな方や不安を持つ方を対象に、ボランティア団体や公民館と連携しながらスマートフォン教室を開催しております。
2.雇用・労働政策
1.就学前教育・保育に携わる職員の処遇改善と人材の確保・定着に向けた取り組みについて
(1)就学前教育・保育に携わる職員の処遇改善や保育人材の確保・定着に向けて、市として更なる取り組みをすること。
(2)就学前教育・保育に携わる職員の配置基準の見直しや休日保育などの働き方の改善に向けて、市として取り組むこと。
<要請の根拠>
就学前教育・保育に携わる職員の処遇改善については、現在、国として対応をはかっていくこととなっているが、処遇水準の高い都市部への流出が問題となっている地域などについては、県や市町村においても更なる処遇改善策が必要である。
また、人材の確保・定着が重要であり、そのためには、処遇改善等加算の対象事業範囲の見直しを市町村に対し働き掛ける必要がある。
保育士については、2024年4月から保育士配置基準の見直しが図られ、3 歳児は「20人に1人」から「15人に1人」へ、4歳児・5歳児は「30人に1人」から「25人に1人」へと配置基準が変更となったが、0歳児~2歳児の配置基準については見直しの対象に含まれなかった。
一方、市町村によっては、よりきめ細かな保育を実施するために国の基準を超える独自の配置基準を定めている自治体もあるが、保育サービスの地域間格差の解消および保育の質の更なる向上に向けては、県が未実施自治体へ主導していく必要がある。
幼稚園配置基準では、1学級の幼児数が35人以下を原則としており、職員の配置数は1学級あたり専任教諭1人をおくことが基準となっているが、それに加え、「預かり保育」「休日保育」の実施など、業務負荷は高くなっているため、改善が必要である。
また、ICT等を活用した事務作業の簡素化や子育て支援員の増員をはかる必要がある。子育て支援員は、研修を受ければ無資格でも子ども子育てに関わる仕事に就ける(市町村単位)ことから、官民の連携により子育て支援を広げていくことが必要である。
【回答】
(1)深谷市では、保育士の確保を目的として、1人当たり月額10,000円を補助し、保育士の処遇改善に努めております。また、市内保育所で新たに就労する保育士の奨学金返済に係る費用の一部を支援することで、市内における保育人材の確保を図り、保育士が働きやすい環境を整備しております。
市立幼稚園の正規職員については、行政職と同様の給料表を使用しており、人事院勧告を踏まえた給与改定により給与を決定しております。会計年度任用職員については、令和4年2月以降、報酬額を3%引き上げる処遇改善を行ったところです。引き続き、幼稚園教諭が働きやすい環境を整備してまいります。
(2)深谷市では、国が定める保育士配置基準に従っており、配置基準を下回る施設はありません。1歳児は県の補助事業を活用して、国の制度を上回る保育士の配置をした場合には補助金を交付しております。また、休日保育を実施している施設はありません。
市立幼稚園では、令和3年度から、全園で「一時預かり」を導入し、平日については14:00~18:00、長期休業中については8:30~18:00の時間で実施しています。導入に合わせて会計年度任用職員を増員し、職員の負担軽減を図っております。
また、全園で園務支援システムを導入し、園児の出欠席の確認や職員の出退勤の管理に活用し、事務作業の軽減を図っております。
引き続き幼稚園教諭が働きやすい環境を整備してまいります。
2.現役世代のがん患者・がん経験者に対する支援について
現役世代のがん患者・がん経験者が治療と仕事や生活が両立できるよう、以下の施策をおこなうこと。
(1)治療と仕事の両立支援に向け、介護保険サービスや小児がん患者の医療費助成制度を利用できない全ての18歳から39歳以下のがん患者に、ヘルパー派遣など生活に必要な支援をおこなうこと。なお、18歳から39歳以下の終末期がん患者については、在宅療養に必要な費用の一部助成など公的支援制度がない市町村は創設にむけた取り組みをおこなうこと。
(2)治療と就業の両立に配慮し、新たにがん患者を雇用する事業所に対し、がん患者就労支援奨励金制度導入に向けた調査・研究をすすめ、新たな制度創設をするなど、がん患者の就業支援に取り組むこと。
<要請の根拠>
国立がん研究センターの推計で、日本人が生涯でがんと診断される確率は2人に1人とされている。また、がん治療の発達により通院での治療をする患者が増えており、今後は経済的な問題や生きる意欲を持ち続けるため仕事と治療の両立を支援することが必要とされる。
特に、治療中のがん患者の18歳から39歳以下については、子育て世代にもかかわらず、症状が重くなっても生活に対する公的支援制度がない市町村もあることから、導入にむけた取り組みが必要である。
また、治療のために離職してしまった労働者が再度就業しやすい環境整備も必要であり、東京都のようながん患者を新規に雇用した事業者に奨励金を支給するなどの支援により、再就職に向けた対策が必要である。
【回答】
(1)若年がん患者の在宅療養支援につきましては、国の支援制度の対象から外れており、患者や家族の負担が大きいことは承知しております。
埼玉県では、今年度より「がん患者ウェルビーイング事業」と称し、がん患者の外見(アピアランス)の変化をケアするためのウィッグや乳房補整具等の購入費の助成や、がん末期患者の在宅療養に必要な訪問介護や福祉用具等の生活支援費用の助成を実施した市町村に対し、補助金を交付する事業を開始しています。
本市におきましても、今年度よりウィッグや乳房補整具の購入費を助成する「アピアランスケア助成事業」を開始いたしました。
若年がん末期患者への在宅療養に必要な費用の助成につきましては、対象者がごく少数であり、また、がん以外の疾病によっても同様の状況が起こりうると思われるため、現在、創設する予定はありませんが、在宅支援の対象者、支援の在り方について、他市町村等の動向に注視し研究してまいりたいと考えております。
がん患者の治療と仕事の両立を支援することは、市といたしましても重要であると考えております。
障害者施策においては、がんにり患したことにより自己の身辺の日常生活動作等が制限され、障害者手帳を取得するに至った場合、障害者総合支援法によるヘルパー派遣などの支援を利用することができます。
※参考 がんによる障害者手帳取得例
・膀胱がんにより、ぼうこう機能障害の手帳を取得
・直腸がんにより、直腸機能障害の手帳を取得
・肺がんにより、呼吸機能障害の手帳を取得
・喉頭がんにより、音声・言語機能障害の手帳を取得
(2)がん患者就労支援奨励金制度に関しましては、今後、国や県の動向を注視しながら調査研究を行ってまいります。
3.交通政策
1.自転車用ヘルメットの着用率向上の取り組みについて
2023年4月に施行された改正道路交通法により、全年齢で自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となった。ヘルメット着用は、自転車乗車時の死亡事故や負傷事故に対し大きな予防効果を発揮するものであり、より多くの自転車利用者にヘルメット着用を波及させるためにも、さらなるヘルメット着用率向上の取り組みをおこなうこと。
<要請の根拠>
埼玉県内の2023年の自転車事故死者は23名(前年比7名増)となっており、いずれもヘルメット未着用となっている。また、自転車が関係する事故の負傷事故件数については、2023年で4,825件(前年比94件増)となっている。
また、埼玉県警によると、2023年7月の調査で県内の自転車ヘルメット着用率は都道府県別で6番目に低い6.1%にとどまっており、着用率を上げることが自転車事故による死者・死傷者を減少・撲滅させることにつながり、ヘルメット着用率を上げることが重要である。
【回答】
市といたしましても、自転車用ヘルメットを着用し頭部を保護することが、自転車事故被害の軽減において最重要であると十分に認識しております。
そのため、令和5年4月に施行の改正道路交通法により、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となったことを受け、街頭キャンペーンなどの各啓発活動において、ヘルメット着用の重要性を更に強く呼び掛けております。
4.福祉・社会保障政策
1.特別支援学校に在籍する不登校児童への支援体制の整備
特別支援学校に在籍する不登校児童生徒を対象に、市が設置する適応指導教室への受け入れ態勢を整備すること。もしくは、学外の施設等を設置し、発達や療育を中心とした専門的な知見を踏まえた支援がおこなわれる体制を整備すること。
<要請の根拠>
公的な不登校児童生徒の支援施策として、市町村の教育委員会が長期欠席をしている不登校の小中学生を対象に、学籍のある学校とは別に学習の援助をおこなう適応指導教室が設置されており、適応指導教室に通うことができれば出席日数として認められる。
しかし、特別支援学校に在籍している児童生徒が不登校状態になった際には、所管が異なること、対応できる教員などが居ないことを理由として、適応指導教室を利用することは困難である。また、市町村の小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒についても、そもそもの設置目的が異なることから、特に発達や療育の面で対応が必要な場合には、出席扱いとなる教室在籍が認められないことも少なくない。
その一方で、全国の特別支援学校における不登校児童は、小学部で2022年度に398人と約0.8%、中学部では840人と約2.6%と決して少なくない割合である(参照:文部科学省『令和5年度学校基本調査』、文部科学省『特別支援教育の充実について(令和5年度)』)。
以上のことから、埼玉県として特別支援学校に在籍している障がいのある不登校児童生徒に対して、適応指導教室のような通学により出席扱いとなる学外の施設などを設けることが必要である。
【回答】
児童生徒が社会的に自立することを目指し、一人一人に応じた学習支援や教育相談体制の充実を図るなど、総合的な不登校対策に努めているところです。その支援策の一つに、学校を長期間欠席している市内在住の小中学生を対象とした教育支援センターである「いきいきスクール」と「いきいきナイトスクール」を市立教育研究所内に開設しております。ここでは、日中のみならず、夜間にも教室を開き、支援を行っております。
現時点では、県立特別支援学校在籍の児童生徒から教育支援センターへの入室に関する問い合わせはございません。
今後、特別支援学校の設置者である県の動向を注視し、連携を図ってまいります。
2.ユニバーサルシート(介助用ベッド)利用の利便性向上について
ユニバーサルシートの設置場所について、利便性が高く誰もが簡易的に検索できるようにすること。
<要請の根拠>
設置場所の情報取得については“GIS(地理情報データベース)”にて検索することになり、実際の利用者からは「スマートフォンの性能によってはブラウザで閲覧が出来ない」、「どうやってアクセスするのか解りづらい」などの声があがっている。
県としては、スマートフォンアプリの提供や、埼玉県公式LINEに機能(アクセスリンク)を追加するなど、利便性の充実をはかる必要がある。また市町村としてもわかりやすい位置情報の提供をする必要がある。
【回答】
ユニバーサルシートの設置場所につきましては、埼玉県において「ユニバーサルシート付トイレがある県・市町村有施設」の調査を行っており、市においても市の公共施設での整備状況を報告しております。調査結果は埼玉県ホームページで公開されており、県内各施設でのユニバーサルシートの設置場所が検索できるようになっておりますので、ご利用いただきたいと存じます。また、今回いただいた「利用者からの声」については、機会を捉えて県へ報告してまいります。
3.ペアレントメンターの積極的活用について
ペアレントメンターの養成数を更に増やすとともに、ペアレントメンターが必要な保護者が利用できるよう周知をすること。
また、WEBを活用した「交流・相談事業」については、働く保護者も参加できる時間帯および休日などにも開設することで、多くの保護者が参加できるようにすること。
<要請の根拠>
令和4年に文部科学省がおこなった調査によれば、15歳未満の発達障がい者数の推計は7.6万人であり、国立障害者リハビリテーションセンターの「発達が気になるお子さんの養育に関するアンケート調査結果」では、『子どものことで相談できる人がいない』に「とてもそう思う」「そう思う」と回答した保護者は19.7% (前回調査時20.4%)であり、『子どもに合った子育ての方法がわからない』と回答した保護者は49.6% (前回調査時51.5%)と、若干の減少は見られたものの、必要な世帯に支援が届いているとは言えない。
依然としてペアレントメンターの必要性は高く、継続的なペアレントメンターの養成および周知が必要である。また、同アンケートにて「休日・夜間も利用できる子育ての相談」に「とても必要」「必要」と回答した保護者は55.4%であり、働く保護者も参加しやすい制度とすることが急務である。
【回答】
現在、当事者同士の交流について未実施ではありますが、要望などを考慮しながら、当事者同士の情報・意見交換の場を設定する際に、ペアレントメンターの活用についても検討してまいります。
また、県が実施する当事者が参加可能な事業について周知してまいります。
4.ケアラー・ヤングケアラー支援の取り組みについて
埼玉県ケアラー支援条例の基本理念である「すべてのケアラーが健康で文化的な生活を営むことのできる社会」の実現をめざし、県内のさまざまな関連機関、市民団体とともにケアラー支援の流れ・体制をつくり、以下の施策をおこなうこと。
(1)ケアラー・ヤングケアラー支援の周知
介護は家族がするものと思い込み疲弊しているケアラーに対して、さまざまな支援があることを周知するよう、特にケアラーと接触の多い病院、診療所、保健福祉介護関係の事業所などに協力を要請し連携をはかること。また、ビジネスケアラーに支援の周知をするよう、企業への広報にも取り組むこと。
啓発活動の推進にあたっては、わかりやすいツール(デジタルツールを含む)を使用し、当事者たちが情報を取得しやすい環境や相談窓口の設置を目指すこと。
<要請の根拠>
ケアラー月間は社会全体への集中的な周知方法として効果があり、日常生活や業務の中で、ケアラーを発見し支援をすることで、ケアラーと家族の状況悪化の予防もできるため、継続した啓発活動が求められる。また、潜在しているケアラー当事者への啓発・周知がより必要であることからも、息の長い啓発活動や支援の取り組みが必要である。
【回答】
本市では、令和6年4月に福祉に関する複合的な問題を抱える方の受け皿となる福祉総合相談窓口「ふくしの窓口」を設置いたしました。この窓口の中で、ケアラー・ヤングケアラーに関する問題についても対応していきます。また、関係機関等と連携し、ケアラー・ヤングケアラーの周知を進めてまいります。
(2)ケアラーの支援体制の整備について
1.ケアラーの支援体制整備のため、「ケアラー支援スタートブック(手引き)」を作成すること。
<要請の根拠>
2023年度の県回答は、大人のケアラーは自分から相談にいき、公的サービスにアクセスできる。ただし、参考になるのでヤングケアラー支援スタートブックを活用し、ケアラーに周知していくとの回答であった。
しかしながら、大人のケアラーも切実な状況の中で、「助けて」と言い出せず孤立していたり、公的な制度を知らないビジネスケアラー(またはワーキングケアラー)が多く存在するという実態がある。
ケアラーが自ら相談し、制度やサービスを利用できていれば、問題の多くは解決しているはずであり、ケアラーの実態を踏まえて、ケアラー支援に活用できる手引きを作成する必要がある。また、ライフステージごとに抱える悩みや問題が異なることを認識し、全ての世代のケアラー支援のための手引きが必要である。
【回答】
ヤングケアラーに関しましては、埼玉県発行の「埼玉県ヤングケアラー支援スタートブック」(手引き)を参考に、関係機関と連携をとりながら支援体制の整備についての取組を進めてまいります。
なお、「ケアラー支援スタートブック」(手引き)」の作成につきましては、今後の県の動向を注視してまいります。
2.子ども・若者育成支援推進法改正を受け、埼玉県におけるケアラー支援条例が対象とするヤングケアラー・若者ケアラーの範囲や支援を狭めないこと。
<要請の根拠>
2024年6月に「子ども・若者育成支援推進法」が改正され、ヤングケアラー・若者ケアラーの明記(※)が成されたが、支援対象の範囲が埼玉県ケアラー支援条例でカバーするヤングケアラー・若者ケアラーより狭いことに強い懸念があり、県の条例を優先するよう取り組む必要がある。
また、支援施策を実施する市町村においてヤングケアラー・若者ケアラーへの認識範囲が狭められ、支援の幅や対象が絞られることがないよう指導をおこなう必要がある。
※子ども・若者育成支援推進法改正案における「ヤングケアラー・若者ケアラーの明記」
修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者その他の社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者・要保護児童、要支援児童(要配慮児童は含まない)
【回答】
「子ども・若者育成支援推進法」におけるヤングケアラーの対象年齢は、18歳未満のこども期に加え、自立に向けた重要な移行期を含む若者期を切れ目なく支えるという観点からおおむね30歳未満を中心とし、状況に応じて40歳未満も対象となり得ると定義しております。
本市といたしましては、上記の年齢に限らず、埼玉県ケアラー支援条例に定義されている「ケアラー・ヤングケアラー」に対して、一人一人の客観的な状況と主観的な受け止め等を踏まえ、関係機関等と連携しながら個別に支援してまいります。
5.環境・資源政策
1.「カーボンニュートラルSAITAMAネットワーク」活動の推進について
市町村の課題に応じた大学や企業等との有機的な連携体制を強化すること。
環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」が活用促進されるよう、地方自治体内の多くの地域で「脱炭素先行地域」に選定されるよう取り組むこと。また、商業地域や工業団地などでも「脱炭素先行地域」選定が促進されるように取り組むこと。
<要請の根拠>
「地域脱炭素ロードマップ」では、目標達成のため、「少なくとも100ヶ所の脱炭素先行地域において、2025年度までに脱炭素に向かう地域特性などに応じた先行的な取り組み実施の道筋をつけ、2030年度までに実行することで農山漁村、離島、都市部の街区など多様な地域において、地域課題を解決し、住民の暮らしの質の向上を実現しながら脱炭素に向かう取り組みの方向性を示すとされている。
2023年11月に第4回目の「脱炭素先行地域」選考結果が発表され、第1回目からの累計で74の自治体提案が選定された。しかしながら、埼玉県で選定されているのは、さいたま市のみであり、今後より多くの埼玉県内の自治体が選定され、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」などの支援措置の活用促進をはかりつつ、自治体としても、必要な政策パッケージの整備をおこなっていくことが重要である。
また、地球温暖化対策計画では、産業部門の削減率の目標を従来の7%から38%へと大幅に引き上げており、住宅街や農山村などばかりでなく、商業地域、工業団地などについても「脱炭素先行地域」選定が促進されるよう、埼玉県は、各自治体が産業界・業界団体と連携強化できるよう働きかけていくことが重要である。
【回答】
本市では、令和3年1月26日に、県内4例目となる「ゼロカーボンシティふかや」宣言を行い、これに伴って、令和5年3月に深谷市環境基本計画(地球温暖化対策実行計画)の見直しを行いました。
脱炭素先行地域については、採択された地域の計画や取組を詳しくみますと、一定の広がりや規模を確保し、住民や地域企業、大学などと一体となった連携体制の構築が必須となっており、選定のハードルは高いものの産業界との連携強化も視野に入れながら研究してまいります。また、既に採択された取組を参考に、地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する地域脱炭素の取組を進めてまいります。
2050年カーボンニュートラルの達成のために、県、市町村、企業、県民など、すべての主体が「ワンチーム埼玉」で対策を実施していく「カーボンニュートラルSAITAMAネットワーク」活動には、当初から参加しており、市町村に求められる役割である、地域に密着したきめ細やかな対策の推進に取り組んでまいります。
2.路上喫煙の課題に対する屋外分煙施設の設置推進について
路上喫煙によるポイ捨てや、望まない受動喫煙対策推進のために地方たばこ税を活用した屋外分煙施設の設置推進をすること。
<要求の根拠>
埼玉県の令和6年度たばこ税歳入予算額は、82億円と県税総額の約1%を占める税となっている。また、2020年4月の改正健康増進法の全面施行とそれらに伴う企業の取り組みなどにより屋内喫煙場所が減少した一方で、受け皿となるべき屋外喫煙場所が増加していないことから、路上喫煙や吸殻のポイ捨てなどによる問題が発生している。
この問題を解決するには、人の集散が多いエリアでの公衆喫煙所の設置をすることが有効と総務省も示している。なお、総務省は、地方たばこ税の継続的かつ安定的な確保の観点から、駅前、商店街、公園などの場所における屋外分煙施設の整備について、県や市を含む地方公共団体へ通達(2024年4月1日)を出しており、その重要性を認識し、地方たばこ税を活用しながら、必要な喫煙場所整備措置を積極的に進めることが重要である。
【回答】
令和2年4月に全面施行された改正健康増進法は、望まない受動喫煙を減らすことを第一の目的とし、これにより多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道・飲食店等において、企業や事業所等の取り組みにより屋内禁煙が推進されていることは認識しております。
併せまして、同法による規制は屋内施設を対象としており、屋外や路上等においては配慮義務に留められておりますが、喫煙者に対しても周囲に対し受動喫煙が生じないよう配慮するという配慮義務を課しております。このため、まずは、喫煙による健康への影響や受動喫煙防止について広く市民の皆様に周知・啓発を継続してまいります。
市では、市内の環境美化の推進を図り、市民の快適な暮らしの確保及び良好な環境の保全に寄与するために、「深谷市くらしの環境美化条例」を制定し、運用しております。
この条例では、市内においてたばこの吸い殻などごみのポイ捨てを禁止しております。
また、たばこの吸い殻などごみのポイ捨てがされないようにするために、「ごみのポイ捨て禁止」の看板を希望に応じて配布・設置し、対策を講じております。
今後も条例の趣旨に基づき市内の環境美化に努めてまいります。
6.教育・子育て政策
1.子育て応援推進について
(1)待機児童解消に向け、引き続き保育所や認定こども園などの整備・拡充、企業内保育所の設置、幼稚園の延長保育などを進めること。
(2)保育所などの利用者のニーズ調査(病後児保育、休日保育など)や隠れ待機児童を対象に保育のニーズ調査を実施し、隠れ待機児童の解消に向け取り組むこと。
<要請の根拠>
2024年4月1日現在の県内の保育所等待機児童数は241人となり、前年から106人減少した。就学前児童数が減少する一方で、認可保育所などへの申込児童数は増加し、2024年4月1日現在の申込児童数は143,486人で、前年から1,873人の増加となった。利用者の多様化するニーズへの調査によって、延長保育、休日保育、病後児保育への対応など保育制度の充実が求められている。保育を希望する方が増えることにより、引き続き、待機児童数解消に向けた取り組みが必要である。特に、働きながら子育てをおこなう人たちの支援に向けては、休日保育、夜間保育、病児・病後児保育、企業事業所内保育施設、休日学童保育などの整備が重要である。
地域子ども・子育て支援事業に休日保育・休日学童保育を明記し整備するとともに、休日保育・休日学童保育が実施されていない地域において、何らかの手段で子どもを預けて就労した場合の費用の補助制度創設や企業が事業所内保育施設を整備する際の助成制度や相談窓口を創設・拡充することが必要である。
病児・病後児保育については、不足している施設を補う取り組みとして、隣接する自治体間の広域連携を活用した取り組み事例がある。東京都町田市・八王子市および、 神奈川県相模原市・川崎市の4市は、域内住民の利便性向上をめざして、いずれの住民も4市が提供する病児・病後児サービスの利用を可能とする広域利用協定を結んでいる。
【回答】
(1)本市では、平成30年度に定員増を目的に既存保育施設の増改築等を行う法人に対し、「待機児童解消施設整備費補助金」を交付し、計119人分の定員増を図りました。
このほかにも、随時、保育施設の増改築を行い、保育ニーズの高い低年齢児を中心に定員増を図ってまいりました。これにより、令和元年度以降、4月1日時点の待機児童は生じておりません。
引き続き、保育ニーズの把握に努め、待機児童が生じないよう必要な措置を講じてまいります。
市立幼稚園では、令和3年度から全園で一時預かり事業を実施しております。平日の預かりだけでなく、夏休み等の長期休業中の預かりも実施しております。
(2)保育所等の利用者及び隠れ待機児童を対象としたニーズ調査の予定は現時点ではございません。深谷市内の保育施設(47園)ではそれぞれの保育方針や理念に基づき特色ある保育を行っており、子どもや保護者に寄り添い、保護者の多様な保育ニーズに対応しております。
2.育児休業と産後パパ育休の取得推進について
日本における育児休業取得率は、女性は8割台で推移している一方、男性は上昇傾向にあるものの女性に比べて低い水準となっている。
政府は、男性の育児休業取得率を2025年までに50%に上げることなどを目標に掲げ、ワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭の調和)の実現に取り組んでいる。
事業者に対し、積極的に男性の育児休業取得を推進していくとともに、企業にとって男性社員が育休を取得するメリットとして「両立支援等助成金」を受けることの周知をおこなうこと。
<要請の根拠>
2022年4月1日から2023年3月31日までの1年間に出産した女性および配偶者が出産した男性の育児休業取得率は、女性の97.8%に対して、男性は23.4%(令和5年度埼玉県就労実態調査報告書による)と極端に低いと言わざるを得ない。前年度(女性 93.1%、男性27.0%)と比較すると、女性は4.7ポイント上昇し、男性は3.6ポイント低下している。
人手不足と言われる中、従業員が育児休業を取得しやすい職場環境を整えることによって、中長期的な人材を確保することが企業としてあるべき姿勢ではないかと考えられる。
2023年6月に策定された「こども未来戦略方針」では、民間における男性の育児休業取得率の目標を令和2025年に50%、令和2035年に85%と定めており、更なる取り組みが必要である。
昨今、育児休業中の同僚の負担を軽減することで、育休を取りやすい職場環境づくりを推進する企業が増えている。例えば、企業事例として、社員の業務をカバーする同僚らに手当などを一時金から反映させ制度を導入している。
中小企業など社員が少ない企業では、1人が育児休業を取ると人手不足による弊害に懸念を持つことから、社員が育児休業を取得すると、「両立支援等助成金」を受けることができることを周知する必要がある。
【回答】
国や県などからの周知等の依頼に基づき、ポスターの掲示、パンフレットの配布など、適切に対応してまいります。
3.学校教育現場でのジェンダー平等・多様性推進について
「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」に基づき、学校教育現場でジェンダー平等や多様性を認め合う視点に立って、性的指向・性自認(性同一性障害を含む)に関する偏見にもとづく言動の払拭や正しい理解の促進のため、児童生徒をはじめ教職員や保護者への研修や相談体制の整備を継続しておこなうこと。
<要請の根拠>
2023年6月23日に公布・施行された「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」に基づき、ジェンダー平等や多様性を認め合う教育現場を実現するために、一人一人が個性と能力に応じて社会に参画する意識を理解することが不可欠であり、そのための継続的な研修が必要と考える。
上記の法律の周知とともに、学校現場における全教職員がこの内容を理解し、生徒への指導ができるよう、性の多様性に係るリーフレットの配布や研修・相談体制の整備を継続しておこない、学校教育現場でのジェンダー平等推進をおこなうこと。
【回答】
学校では、「男女平等教育資料」や「男女平等意識を高める校内研修資料」、「性の多様性の尊重に係る教職員用リーフレット」などを活用して、校内研修を実施しています。
今後も、性同一性障害をはじめとした性的マイノリティに係る人権問題の研修を継続的に実施してまいります。
また、特別の教科道徳や学級活動等を通してジェンダー平等の視点に立った指導を行い、このことに起因するいじめなどが起こることのないよう、児童生徒への指導を行うとともに、保護者に対しては、授業参観、懇談会、入学説明会など様々な機会に周知し、学校・家庭・関係機関等との相談体制を整備してまいります。
4.部活動の地域移行による参加者費用負担について
部活動地域移行による地域クラブ活動に参加する生徒の参加者費用負担支援として、地域移行している文化・スポーツ団体での活動において、参加する生徒に対する補助をおこなうこと。特に、費用負担に関して、金銭的側面から断念せざるを得ない生徒が出ないよう、困窮家庭に対する補助金の支援をおこなうこと。
<要請の根拠>
教員の長時間労働が問題視されており、長時間労働是正には業務削減・教職員定数改善が必要と言われている。学校の働き方改革の視点から、教員の業務負担の軽減策の一つとして地域移行が進められている。
2022年12月に、スポーツ庁と文化庁の両庁名で「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」が策定された。地域移行はすでにモデル校で試行的に取り組まれているが、公立中学校の休日の部活動については、2023年度から2025年度までの3年間を改革推進期間として地域移行に段階的に取り組み、可能な限り早期に実現することを目指すとしている。
地域移行のメリットとして、「生徒の選択肢が広がる」「専門的な指導が受けられやすくなる」「教員業務のスリム化が期待できる」などがあげられている。一方、デメリットとしては、「指導者や受け皿の確保が容易ではない」「生徒の安全上の不安がある」「保護者の経済的負担が求められる」などがあげられている。特に、費用負担に関しては、金銭的側面から断念せざるを得ない生徒が出ないよう、補助金などの支援が必要とされる。
なお、茨城県つくば市においては、部活動地域移行による地域クラブ活動に参加する生徒の費用負担への支援として、地域移行している文化・スポーツ団体での活動において、困窮家庭の利用料を補助している。
【回答】
深谷市では、令和5年度より国の実証事業に参加し、補助金を活用しながら部活動の地域移行の在り方を研究しております。保護者の費用負担に関しましては、今年度は、活動費として活動1回あたり200円と保険料として800円を徴収しておりますが、金銭的な理由で地域クラブ活動への参加を断念せざるを得ない生徒が出ないよう、就学援助世帯からは活動費に関しては徴収せず、保険料の800円のみで活動に参加できるよう体制を整えて実施しています。
7.人権・ジェンダー平等政策
1.パートナーシップ・ファミリーシップ登録制度について
(1)パートナーシップ制度では、埼玉県としての導入をはかること。
また、市町村ごとに制度の内容が異なるため、県と市が連携し、利用可能な行政サービス内容の統一をすすめること。
(2)ファミリーシップ制度の普及が進んでいないことから、制度の導入について更なる検討をすること。
<要請の根拠>
社会全体で、性的指向や性自認(性同一性障害含む)に関する認識が深まり、県内でも62の自治体(全63自治体)でパートナーシップ制度が導入され、残る川口市でも導入の意向がされている。しかし、市町村ごとにパートナーシップ制度の内容が異なるため、市町村を越えて異動した場合や、他の市町村の施設を利用する場合などでスムーズに適用できない事があり、市町村の制度内容の連携が望まれている。
また、県内の市町村でパートナーシップ制度が広がりを見せる中、ファミリーシップ制度の普及はあまり進んでいない。ファミリーシップ制度ができることで、子どもを学校や保育園に迎えに行った際の引き渡しや、子どもが病気で病院にかかったときなどに、家族として周囲からの理解を得やすくなるとされており、制度の導入を進めることを求めるものである。
【回答】
(1)制度内容につきましては、本市では、各課の協力を得て、パートナーシップ宣誓者を、配偶者(事実婚を含む)または親族とみなして利用できるサービスについて充実させるよう努めており、今後も拡充を図っていく予定でございます。
パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携につきましては、埼玉県内の自治体で、「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結し、宣誓者が県内の自治体間で移動した場合の手続きの簡素化等、利便性の向上を図っております。
(2)本市においても、パートナーシップ宣誓をした方の双方または一方の子等で継続的な共同生活をしている場合に、ファミリーシップにある者として、パートナーシップ宣誓に含むことができるファミリーシップ制度の導入を予定しております。
8.防災政策
1.市の防災対策について
あらゆる災害に対し、全ての住民が安心して支援を受けられる環境整備を推進すること。
(1)災害時における避難所(防災拠点校の体育館など)機能について
多発する集中豪雨などの自然災害に対応できる防災拠点校を増やし、優先順位をつけて、体育館などの避難所機能の充実をはかること。
具体的には、すべての対象施設に対して、計画的にエアコン機器の設置・増設、停電時に利用できる電源の確保、および備蓄品の保管に取り組むこと。
<要請の根拠>
河川に囲まれた埼玉県においては、水害対策を優先して防災対策に取り組まなくてはならない。中でも災害時の避難所となる防災拠点校の整備は、構造や周囲の状況、立地場所などを鑑みて、優先順位を付けて取り組むことが必要である。
また、多くの防災拠点校は、建設時、大地震を想定して整備したものであり、整備されて25年余りが経過し、設備の老朽化が進んでいる。
防災拠点校は、いざという時に住民が安心して避難できることが重要であり、地震だけではなく、豪雨などの自然災害においても、安全確保に役立つための整備が必要である。
そのためにも、全ての対象施設において、計画的にエアコン機器の設置・増設をおこない、停電時に利用できる電源の確保、および備蓄品の保管に取り組む必要がある。
また、豪雨災害は梅雨期から夏季にかけて発生することが多く、避難先においての熱中症などの2次被害を発生させない環境整備が必要である。
【回答】
本市では災害時に避難所となる12公民館に体育室が設置されており、公民館が主要な避難所となります。そのうち、5公民館にエアコンが設置済みであり、設置率は41.7%となっているほか、会議室にはエアコンが整備されていることから、可能な限り活用してまいります。
なお、今後、公民館に設置したエアコンのランニングコストを調査しつつ、また、停電時の電源の確保も併せて、引き続き検討してまいります。
市立中学校の体育館に関しましては、令和7年度にエアコンを整備する予定でおります。市立小学校の体育館は、令和7年度に設計を実施する予定であり、今後、計画的に体育館へのエアコンの整備の実施に努めてまいります。なお、普通教室や特別教室にも空調設備が整備されておりますことから、こちらも可能な限り活用してまいります。
備蓄品の保管につきましては、災害時、交通網の遮断等により、速やかに避難所に物資を運び込めない可能性を想定し、市内防災倉庫のほか、優先的に開設する避難所についても食料や飲料水、衛生用品等の必要最低限の物資を設置しております。
(2)災害時、防災拠点における性的マイノリティに対する支援について
防災拠点において相談員となる職員を対象に、性的マイノリティ支援について記載した「埼玉県地域防災計画」「避難所の運営に関する指針」に沿って、災害時に性的マイノリティへの支援活動ができる研修会を継続的に開催すること。
<要請の根拠>
災害時には様々な要素において生活が困難になることから、性的マイノリティの視点からの配慮も必要であり、誰もが安心して生活できる社会の構築をめざすことが必要である。
「埼玉県地域防災計画」には、避難所におけるLGBTQなど性的少数者への支援についての記載があり、誰でも安心して相談できる環境整備には、性的マイノリティを含めた対応を徹底するため、相談員(職員)への実践的な研修が必要である。
【回答】
防災拠点の、特に避難所に関しては、その運営に多くの市職員が従事することから、市職員全員を対象とした性の多様性に関する研修会を定期的に開催してまいります。
(3)防災会議委員の女性割合向上について
市防災会議委員の女性割合向上を推進すること。
<要請の根拠>
災害は全ての人の生活を脅かすが、女性や子どもなどの災害脆弱な状況にある人々がより多くの影響を受けることが指摘されている。特に、災害対策においては、内閣府男女共同参画局による「女性活躍・男女共同参画の重点方針2024」において、「防災・復興に関する政策・方針決定過程への女性の参画拡大」や「防災の現場等における女性の参画拡大」などに記されているように、女性の視点を入れた災害対応がおこなわれることが災害に強い社会の実現のためには不可欠である。
市においても、市防災会議への女性の割合を早期に30%達成することが望ましいと考える。
【回答】
深谷市防災会議委員46人中、女性委員は1人で、委員に占める女性の割合は2.2%となっております。
女性の視点を取り入れた災害対応の充実に向けて、今後も女性委員の割合が向上するよう努めてまいります。
(4)首都直下型地震等、マグニチュード7クラス以上の地震発生への対応について
1.マグニチュード7クラス以上の地震発生に耐久できる水道管(送水管)の耐震管への敷設替えを、病院や避難所等の施設へ通ずる水道管を優先的に実施すること。
<要請の根拠>
平成24、25年に埼玉県が発表した「埼玉県地震被害想定調査報告書」では、今後30年間において、南関東地域でマグニチュード7級の地震が発生する確率は70%としており、いつ大規模な地震が発生してもおかしくない状況にある。
また、2022年4月時点では、県営水道の送水管路延長約777kmのうち、耐震管の使用率は約40%であり、地盤状況を考慮した耐震適合率でも66%となっている。
2024年1月に発生した能登半島地震においても、被災者の声からは1日も早い水道の復旧を望む声が多く、特に、命に直結する病院や避難所などへの施設に通ずる水道管を優先的に耐震管へ変更する敷設替えをおこなうことが重要である。
なお、首相は「今年度内にすべての自治体において、上下水道耐震化計画の策定や更新を進める」としており、その方針を理解し、県内全ての自治体で上下水道耐震計画の策定や更新がなされるよう推進することが必要である。
【回答】
本市では、令和3年度から病院や避難所など重要施設に接続する管路等の耐震化を計画的に進めております。
また、今般、上下水道耐震化計画を策定し、計画に位置付けた管路の耐震化を優先的に進めてまいります。
2.非常参集訓練、図上訓練の充実による市での災害対応レベルの向上をはかること。
<要請の根拠>
日本の災害対策の法体系の基本は、市町村が主たる対応者であり、そのフォローをするのが都道府県となっていることから、市町村や都道府県の役割が非常に重要である。
災害対応能力を上げるためにも、常日頃から実践的な訓練をおこない、対処能力を上げる必要があり、非常参集訓練や図上訓練を頻繁におこなう必要がある。
【回答】
災害時に公助の役割を担う市職員の対処能力を向上させるため、これまでも防災担当職員で図上訓練等に取り組んでいるところでございますが、今後も機会を捉えて、職員を対象とした非常参集訓練や図上訓練を行ってまいります。
3.災害時における通信断絶を想定した衛星通信インフラの確保をはかること。
<要請の根拠>
巨大地震の発生時には、多くの地域での通信断絶が見込まれ、既存の通信インフラでは災害救助要請などの連絡手段が絶たれてしまうことも想定しておかなければならず、衛星インターネット機器の設置・運用を防災計画に盛り込むことは非常に有効な災害対策となる。衛星インターネットは設置の容易さ、静止軌道衛星による広範囲通信の網羅などの理由から非常に有用であり、人命救助や復旧活動などの要請が滞りなくおこなえることが期待できる。東京都を含む他県の導入例を参考に、埼玉県および各市町村においても導入・検討を進める必要がある。
【回答】
災害時における通信断絶に備えて、災害救助要請などの音声通話による通信手段を確保するため、衛星携帯電話を導入・運用してきたところでございますが、衛星インターネットの設置につきましては、他自治体の導入例を参考に、研究してまいります。
4.大量アクセスに耐えうる行政サイトを構築し、大規模災害に備えること。
<要請の根拠>
広域におよぶ震災発生時には、一人一台の個人端末所持が一般化する昨今において、非常に多くの人々が一度に災害情報へとアクセスすることが想定される。このことから、一極集中接続に耐えうるネットワーク(通話回線輻輳回避)やサーバーインフラの増強など、強靭な行政サイトの構築をはかる必要がある。
【回答】
令和4年度末にホームページ管理システムのサポート終了に伴い、後継サービスへの乗せ換えを行いました。これに伴い、現在は、サーバーを増強しCDNサーバーと呼ばれる中間サーバーが設置されているため、閲覧が集中してホームページが途切れてしまう可能性が低くなり、災害時も含め、より安定的な運用が可能となっています。
また、災害時など、ホームページのアクセスが集中する状況になった場合は、画像やカラー表示を使用しないシンプルな画面表示に切り替える、『軽量化』を行います。
このような対策を講じているため、行政サイトの強靭化は図られているものと考えております。
5.災害時協力企業マップの作成と配布を進め、災害に備えること。
<要請の根拠>
平常時から自治体企業が協定を結び、緊急時には迅速な対応ができるよう準備を整えることとあわせ、緊急時には十分に機能することが望ましい。
埼玉県においては、「ミンナ防災」の取り組みの中で、埼玉県地域防災サポート企業・事業所を紹介して取り組んでいる。しかしながら、利用者からは、マップ上での表記でないため、いざという時には活用できない。
より利用しやすい、活用しやすい取り組みとして、災害時協力企業マップの作成と配布を進め災害に備えること。また、市町村においても、災害時協力企業マップ作成の前進がはかられるよう、県は各市町村に対しての指導を進める必要がある。
また、各市町村においては、災害時協力企業への取り組みを継続しながら、県と連携した、災害時協力企業マップの作成と配布を進め災害に備えることが必要である。
【回答】
本市では、災害時の応急・復旧対策を円滑に実施するため、様々な業種の企業・事業所等と協定を締結し、平時から災害に備えております。
ご指摘の埼玉県地域防災サポート企業・事業所に関しましても、災害時における防災力の向上に資するものであると考えておりますので、県と連携し、マップの作成や配布について検討してまいります。
(5)台風や線状降水帯などによる水害への対応について
洪水発生時の垂直避難を円滑にするため、避難指定ビルなどの設定をおこなうこと。
<要請の根拠>
近年、地球の温暖化に伴う台風の大型化や線状降水帯の頻繁な発生など、水害が起こる確率は非常に高くなっている。
埼玉県においても、2019年の台風による被害は記憶に新しい。当時、県北部において緊急避難指示が出された際、避難者はどこに避難してよいのか分からず、自己判断にて近隣の高いビルに駆け込み避難していた実態がある。
浸水リスクの高い地域においては、避難ビルや高層建物を指定し、住民が垂直避難できるよう整備する必要がある。
【回答】
水害から命を守るためには、平時から避難のタイミングや避難先を決めておき、躊躇うことなく早めに避難をすることが大切でありますので、引き続き、ハザードマップの活用講座などを通じて周知・啓発に努めてまいります。
なお、避難指定ビル等の指定に関しましては、他自治体の例を参考に、研究してまいります。
(表記を一部変更して掲載しております)
(令和7年3月24日)
|
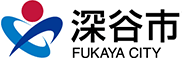




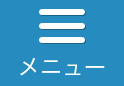

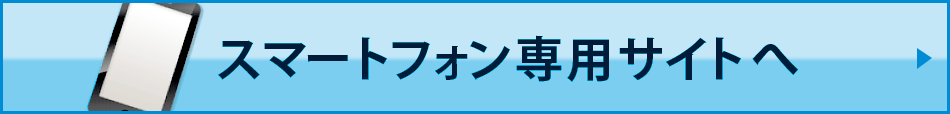
更新日:2025年05月08日