高額療養費制度について
高額療養費の支給条件
同じ月内の医療費(差額ベット代、食事代などは除きます)が高額になったとき、次の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
| 所得区分 | 自己負担限度額(3回目まで) | 4回目以降 |
|---|---|---|
| ア 901万円超 | 252,600円+1パーセント 1パーセントは医療費が842,000円を超えた分の 1パーセント |
140,100円 |
| イ 600万円~ 901万円以下 |
167,400円+1パーセント 1パーセントは医療費が558,000円を超えた分の 1パーセント |
93,000円 |
| ウ 210万円~ 600万円以下 |
80,100円+1パーセント 1パーセントは医療費が267,000円を超えた分の 1パーセント |
44,400円 |
| エ 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| オ 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
| 所得区分 | 自己負担限度額 (外来) |
自己負担限度額 (外来+入院) |
|---|---|---|
| 課税所得690万円以上 現役並み所得者3 |
252,600円+1パーセント 1パーセントは医療費が842,000円を超えた分の1パーセント <4回目以降:140,100円> |
|
| 課税所得380万円~690万円未満 現役並み所得者2 | 167,400円+1パーセント 1パーセントは医療費が558,000円を超えた分の1パーセント <4回目以降:93,000円> |
|
| 課税所得145万円~380万円未満 現役並み所得者1 | 80,100円+1パーセント 1パーセントは医療費が267,000円を超えた分の1パーセント <4回目以降:44,400円> |
|
| 一般 | 18,000円 <年間上限額:144,000> |
57,600円 <4回目以降:44,400円> |
| 住民税非課税世帯 低所得2 |
8,000円 | 24,600円 |
| 住民税非課税世帯 低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
- 高額療養費支給対象になった場合には、世帯主あてに申請書を送ります。申請書が届いたら、保険年金課または各総合支所市民生活課の窓口で申請をお願いします。
- 高額療養費の申請書等は原則、診療月の3カ月後以降に郵送しますが、医療機関の保険請求を元に計算を行うため請求状況によって前後しますのでご了承ください。
- 申請では、医療費の領収書を確認しますので、申請が済むまで大切に保管をしてください。
手続きに必要なもの
- 支給申請書
- 領収書(高額療養費の算定対象となったもの全てが必要になります。)
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
- 来庁されるかたの本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きのもので、有効期間内のもの。お持ちでない場合は、住所、名前等が確認できるもの2点以上。)
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び対象者のもの)
- 委任状(同一世帯以外のかたが窓口に来る場合)
「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付について
「限度額適用認定証」を医療機関へ提示することで、月ごとの窓口での自己負担が最初から限度額(上記の表参照)までにとどめられます。
「限度額認定証」の提示により窓口負担が限度額までにとどめられるのは、ひと月のうちに同一の医療機関で受診した分のみです(ただし、同一の医療機関で入院と外来を受診した場合は、それぞれ別に計算されます)。複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの医療機関で限度額まで請求があります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
注意事項
自己負担限度額は、月ごと、医療機関ごとに計算されます。ただし、同じ医療機関でも医科と歯科は別計算、また外来と入院も別計算となります。
保険外診療や、入院時の食事代、差額ベッド代等は限度額適用の対象外となります。
住民税非課税世帯(世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税の世帯)のかたが申請された場合、入院時の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
対象者
・深谷市国民健康保険に加入しているかた
・国民健康保険税を滞納していないかた
70歳以上のかたは限度額適用認定証が不要な場合があります。
70歳以上のかたで、所得区分が「現役並み所得者3」または「一般」の場合は、限度額適用認定証がなくても自己負担限度額までの支払いとなります。そのため、限度額適用認定証の申請は不要です。
申請方法
交付を希望されるかたは、以下のとおり申請してください。
なお、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、原則申請した月の1日(郵送申請の場合、申請書が到着した日の属する月の1日から毎年7月末日です。有効期限後も引き続き必要なかたは、8月以降に再度申請してください。
申請に必要なもの
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・被保険者番号のわかるもの(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
(注意)申請できるのは本人か同一世帯のかたです。別世帯のかたが申請する場合は、委任状が必要となります。
入院時の食事代について
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担します。
住民税非課税世帯のかたが申請された場合、入院時の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
(注)令和7年4月1日から標準負担額が下の表のとおり変更になりました。
| 所得区分 | 食費 (1食につき) |
|
| 一般(下記以外の人) | 510円 | |
| ・住民税非課税世帯 | 過去12ヵ月の入院日数が 90日までの入院 |
240円 |
| ・低所得者2 | 過去12ヵ月の入院日数が 90日を超える入院 |
190円 |
| 低所得者1 | 110円 | |
注意事項
住民税非課税世帯(オまたは区分2)の期間で、直近1年間の入院日数が90日を超える方は、入院日数の届出をすると、翌月1日から入院時の食事代が1食190円に減額されます。
入院日数が90日に達した当月中に速やかに申請をお願いします。申請が遅れた場合、遡って減額することはできませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
・入院の領収書
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・世帯主および対象者の個人番号が確認できるもの
(注意)申請できるのは本人か同一世帯のかたです。別世帯のかたが申請する場合は、委任状が必要となります。
注意事項
・国民健康保険税の納付状況等により、区分を確認できない場合があります。
・住民税非課税世帯(オまたは区分2)の期間で、直近1年間の入院日数が90日を超えるかたは、別途手続きが必要です。
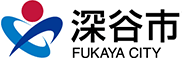




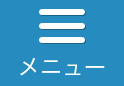

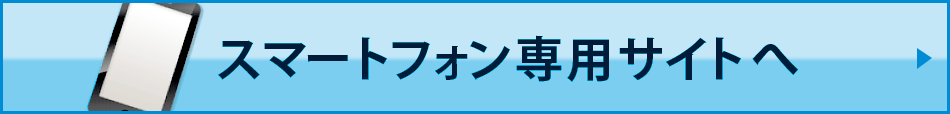
更新日:2025年04月01日