児童福祉法における障害児支援
児童福祉法に基づき、児童の保護者とともに、身体に障害のある児童(18歳未満)、知的障害のある児童(18歳未満)または精神に障害のある児童(18歳未満)に対し、心身ともに健やかに育成するための支援を行います。 障害児通所支援とは、児童発達支援、放課後等デイサービスおよび保育所等訪問支援をいいます。
障害者総合支援法によるサービス(障害福祉サービス)については下記からご確認ください。
障害児通所サービスを利用するまでの流れ
1 相談・申請
利用したいサービスについて障害福祉課に相談していただき、申請をしてください。また、サービス等利用計画案などの作成も必要となります。
難病のかたは、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をお持ちになり、窓口に支給申請をしてください。
2 概況調査
申請時に生活や障害の状況についての調査を行います。(場合により訪問調査を行うこともあります。)
3 決定通知
生活状況やサービスの利用意向を踏まえるとともに、サービス等利用計画案の提出のもと支給決定が行われ、通所受給者証が交付されます。
4 契約
受給者証が交付されたら、利用者自らが選んだサービス事業者または施設に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。
5 サービスの利用
サービスを利用します。利用者負担がある場合にはサービス事業者または施設にお支払いください。
障害児通所サービスの種類と内容
| サービス種類 | サービス内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 (多子軽減措置の対象) | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 | 療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児。 具体的には次のような例が考えられます。
|
| 放課後等デイサービス | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 | 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園および大学を除く。)に就学していて、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障害児 |
| 保育所等訪問支援 (多子軽減措置の対象) | 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 | 保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児で、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児 |
費用
サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額負担上限額の設定)となります。また、定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得のかたに配慮した軽減策が講じられています。
| 区分 | (障害児の利用負担)世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
収入状況を確認する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
放課後等デイサービスの更新について
放課後等デイサービスの更新申請時に障害者手帳(身体・療育・精神保健福祉手帳)を所持していないかたは、小学校・中学校・高等学校に進学時、医師の診断書等が必要になります。詳しくは下記をご参照ください。
電子申請について
下記については電子申請することができます。
新規申請のかたは窓口申請となります。
障害児通所サービス(児童発達支援)の更新申請ができます。
障害児通所サービス(放課後等デイサービス)の更新申請ができます。
障害福祉サービス(行動援護、短期入所等)の更新申請ができます。
地域生活支援事業(移動支援、日中一時、訪問入浴、デイサービス)の更新申請ができます。
地域生活支援事業(移動支援、日中一時、訪問入浴、デイサービス)更新申請
計画相談支援依頼(変更)の届出ができます。
計画相談支援事業所の変更については、新旧事業所了承のもと申請してください。
障害福祉サービスに関する受給者証の再交付申請ができます。
地域生活支援サービス受給者証の再交付申請ができます。
障害福祉サービスに関する申請内容(氏名、居住地、連絡先等)の変更届出ができます。
障害福祉サービスの支給量等の変更申請ができます。
地域生活支援事業の支給量等の変更申請ができます。
地域生活支援事業(移動支援、日中一時、訪問入浴、デイサービス)変更申請 (18歳未満)
多子軽減措置について
1 内容
障害児通所支援を利用している児童と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園・保育園などに通っている場合、障害児通所支援の利用者負担額を引き下げます。
2 対象児とその保護者
以下を満たす児とその保護者
・同一世帯の兄または姉が幼稚園など(保育所、認定こども園等含む)に通所している。
・障害児通所支援の支給決定をうけ、かつ通所利用している。
3 多子軽減の対象となる障害児通所支援
1 児童発達支援 2 医療型児童発達支援 3 保育所等訪問支援
4 対象児の登録と決定について(多子軽減措置に伴う利用者負担額減額・免除の手続き)
上記の2「対象児とその保護者」及び3「多子軽減の対象となる障害児通所支援」に該当する場合は、以下の書類による登録の手続きが必要となります。
1 「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」
2 兄または姉の幼稚園などの通園証明書
3 市から決定された「通所受給者証(注釈1)」(ピンク紙) (注釈1:持っているかたのみ)
5 多子軽減額の計算方法
障害児通所支援を利用している児童と同一世帯に、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設に通うまたは障害児通所支援を利用する児童がいる場合、障害児通所支援を利用する児童が、
- 第2子:障害児通所支援に係る費用総額の100分の5の額
- 第3子以降なら無償
と、所得区分ごとの従来の負担上限月額を比較して低いかたを利用者負担上限月額とみなします。
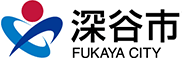




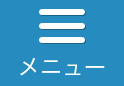

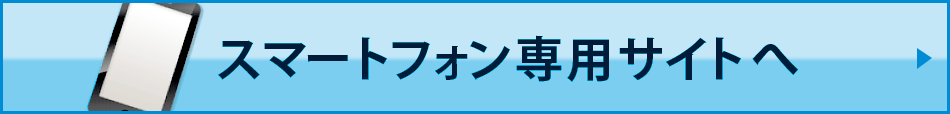
更新日:2025年03月10日