王国植物だより(冬)
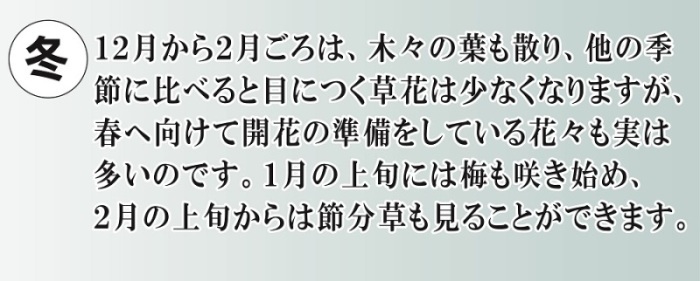
・種目の後の月の表示は見ごろの時期を表しています。
なお、原則としてそれぞれの草花の写真を撮影した時期を開花期(見ごろの時期)と見なしています。植物図鑑等で開花期として表記されている時期と異同がある場合や、撮影した時期以前から既に開花している場合もあります。また、その年によって開花状況が異なることや、開花しない場合もありますので、あくまでも参考としてご覧ください。
スノードロップ(11月中旬から)

地中海沿岸地方原産。うつむいて咲くランプのような形をしています。ものの本によると「楽園を追い出されたアダムとイブをなぐさめるため、天使が雪をこの花にかえた」という伝説があるそうです。

赤い実を持つ冬の木々(12月上旬から下旬)
冬には赤い実をつける木や植物が多々見られます。冬という季節自体は枯れたイメージですが、赤い実がささやかな華やかさを演出してくれているようです。年の終わりに王国で見られる赤い実たちを最初に紹介しましょう。
クリスマスホーリー(セイヨウヒイラギ) ヨーロッパではクリスマスの飾りや魔除けとして使われます。王国でも、ボランティア活動や王国自然クラブでのクリスマスリースづくりの素材として使用することがあります。

ナンテン(南天) 「難を福に転ずる」の語呂合わせから縁起のいい木と見なされ、玄関脇に植えられることがある木です。他にも魔除け、火災除けのため床の間などに飾られたり、病魔除けとして出産祝いに赤飯の上に置かれたりと、日本人の民間信仰には欠かせない植物と言ってもいいかもしれません。薬草として、実は咳どめ、葉は二日酔いに効くと言われています。


ナンテンの花。6月末に撮影。この時期になるとあちこちの民家の敷地内で咲いているのをよく見かけます。
イイギリ 真っ赤な葡萄のようなこの実は、「イイギリ」のものです。漢字では「飯桐」と書き、昔は葉で飯を包んだことからこの名があるとか。上で紹介した南天の実に似ていることから「ナンテンギリ」とも呼ばれるそうです。サステナブルガーデンで撮影しました。


大体隔年ごとに鈴なりに実を付けます。

センリョウ お正月の縁起物。センリョウとマンリョウです。区別の仕方は、 実が上につくのがセンリョウ、下がマンリョウです。漢字では「千両」と、経済のにおいのする字を書きますが、江戸時代より前は「仙寥」と書いたそうです。印象が全く違います。

マンリョウ こちらがマンリョウです。センリョウ・マンリョウとひとくくりで扱われることがよくありますが、センリョウはセンリョウ科、マンリョウはサクラソウ科と、全く違う仲間だとか。実の美しさがセンリョウより優るので、マンリョウと呼ばれています。

ニシキギ(下3枚とも) 漢字では「錦木」と書かれるこの木は、秋には小さい葉が真っ赤に紅葉し、小さな実も赤く結実します。実の表面は薄い皮でくるまれており、中にとても硬い小粒の種が入っています。紅葉の美しさを錦の織物に例えて名付けられました。ニシキギは、枝からコルク状の平べったい板のような翼(よく)と呼ばれる部位が飛び出てくるのが特徴的です(3枚目の写真)。この翼を日干しにして乾燥させ、煎じて服用します。薬効は主に「月経不順」です。


ニシキギ 全景

この昆布のような部分が翼。薬になる部位です。
ビナンカズラの実(12月上旬から)

冬場に姿を見せる「赤い実」たちの中でもっともユニークな形を持つと思われるのが、このビナンカズラ(サネカズラとも)の実です。5ミリほどの実が丸くまとまって、一つずつ垂れ下がります。医療系の図解で体内にはびこる病原体や細菌を表す時にこんな形で描きそうです。つやつやしていて美味しそうですが、苦みや渋みが強く、とても食べられたものではないとのこと。美味しければ冬場に可食できるものを見逃さない鳥たちがすでについばんでいるはずなので、鳥にすら相手にされないことが、むしろきれいな造形を保つ秘訣になっているとも言えそうです。ただ、これを乾燥させて漢方薬として使うとか。
気になる名前の由来は、茎から出る粘液を整髪料に使ったため、とのことで、残念ながら「赤い実」は無関係の模様。「なぜ美女ではないのか?」という素朴な疑問も発生しますが、そこは興味のあるかたが追及してください。

ナゾの生命体のような造形・・・

ツバキ・サザンカ(12月上旬から)
園内にはツバキ・サザンカ園をはじめ各所にこれらの品種が散在しています。咲く順番はサザンカが早く、12月初頭ごとから見ることができます。ツバキ・サザンカの一般的な見分け方としては、ツバキは葉が丸っこく、花ごとボトリと落ちる。サザンカは葉が細長く縁にギザギザ(鋸歯)があり、花弁一枚一枚がハラハラと落ちるという点です。12月中はおおむねサザンカが主役ですが、この時期に咲く「寒椿」も幾種類か見られます。多くのツバキの開花時期は年明けの2月頃からです。


サザンカ

サザンカ

サザンカ

寒椿

寒椿

寒椿の一種、「白侘助」。侘助は古くから茶花として親しまれ、筒形の小花がどことなくはかない印象を与える。
ロウバイ(12月中旬から)
ロウバイは早いものは12月半ばごろから開花します。中国原産で、「カラウメ」とも呼ばれます。花の色や質感が「蜜蝋」に似ていることや、蝋月(陰暦の12月)が開花期であることから、「蝋梅」の名があります。一般的なロウバイは、中央の芯の部分が次第に黒っぽくなってきますが、この部分が黄色いままで、且つ花が大きい「ソシンロウバイ」という種類もあり、こちらの方が人気は高いそうです。 (下はせせらぎ通りに咲くロウバイ)


全体が黄色いため、ソシンロウバイかと思われます。通用門側の駐車場と、南門付近の緑地の中にあります。
冬のバラ(12月)
「冬そうび」という言葉もあるように、冬に咲くバラは花の少ないこの時期でも広く親しまれています。ローズガーデンにも数種類の冬バラが咲いています。このローズガーデンの位置する場所は風が強く、中央にある池には5センチほどの氷が張ることもあるくらい厳しい環境のはずですが、冷たい風に揺れながらも小さく美しく咲いているバラの姿には希望を感じます。






ビワの花(12月上旬から)

冬場の厳しい環境に花を咲かせるというだけで、エライなあと思いますが、必ずしも目立たない花なのに毎年必ず咲くビワには特にその思いを強くします。長細い艶のある葉の上に、茶褐色で毛の生えた軸からひっそりと黄身がかった白い小花を群れをなして咲かせます。甘い芳香を放ち、虫もよく集まるそうです。
ウグイスカグラ(1月下旬から3月ごろ)

ウグイスカグラは冬場に咲くスイカズラ科の落葉低木です。王国にあるのは高さは1メートル程度の細い木で、3メートルにまで成長するものもあるようです。1月の終わりごろからピンクのラッパ状の花を下向きにいくつも咲かせます。花はほんの数センチととても小さく、微風にも揺れるので、非常に写真に撮りにくい花でもあります。漢字では「鶯神楽」と面白い字面になりますが、名前の由来はよくわかっていないそうです。
バイカオウレン(1月中旬から3月ごろ)

2023年に植物学者・牧野富太郎が主人公のNHKの朝ドラが放映され、そこで注目されたことが一つのきっかけで緑の王国のガーデンに仲間入りした花です。漢字では「梅花黄蓮」と書き、梅の花に似た花をつけます。セツブンソウにもやや似た感じがします。初めは地面を這っているようですが、だんだん茎が立ち上がってきます。花に見えるのは額とのことです。

カンザキアヤメ(1月中旬から2月下旬)

カンザキアヤメは晩冬から初春に咲くアイリスの一種類です。時たま晩秋に咲くこともあるそうです。緑の王国では、花仲間ガーデンの池のほとりの一か所に毎年咲きます。群生というほどではありませんが、次々と咲くので意外と長い期間楽しめます。全体的に薄青い爽やかな色合いで、アヤメらしく花弁の中央に黄色の筋が入っています。原産地はギリシャ、トルコやアフリカ北部です。
ロニセラ・フラグランティシマ(1月下旬)
フユザキニオイカズラとも呼ばれるスイカズラ科のこの花は、1月末から2月初めのもっとも寒い時期に花を咲かせ、芳香を放ちます。雪の降るような極寒の日でも、花の上に雪を載せてそのまま咲いているので、寒さには耐性が強いのでしょう。まきばガーデンに1メートル60センチほどの木立となっており、満開の時期には木全体と言っていいほどにたくさんの花をつけます。


1月の初旬に先走りのように咲いているのもありますが、本格的な見ごろはあと1か月はあととなります。
フクジュソウ(1月中旬から2月)
江戸時代から新春を彩る花(ガンジツソウという異名もある)として、愛好家たちによる育成、栽培が行われている根強い人気を持つ花です。緑の王国では山野草ガーデンとカエデ通りの梅園に毎年咲きます。年末にそっと咲くあたりの土を除けてみると、ひづめのような白い芽が出ており、これもちょっとした春のきざしと思えます。


フクジュソウの芽です。12月下旬から1月ごろに地表の土をそーっとかき分けてみると、芽を出している様子がわかります。

梅園(12月下旬から2月までの様子)
ふかや緑の王国にはおよそ100種類の梅があります。それぞれ咲く時期には差があり、紅梅、白梅や薄紅、濃厚な紅など色も形も様々です。毎年3月上旬の「梅まつり」の時期にはそうしたたくさんの梅の花が楽しめますが、近年梅や桜などバラ科の植物を侵食する「クビアカツヤカミキリ」が入り込み、緑の王国の梅園にも被害が発生しています。





クロッカス(2月中旬から3月上旬)
春告げ花として広く親しまれているクロッカスです。緑の王国では、ハナミズキ通りに沿った芝生と花仲間ガーデンに毎年芽を出し花を咲かせます。特に紫色のクロッカスは、陽の光を浴びると艶々と輝いて思わず触ってみたくなります。




色も様々、斑入りのものもあります。
クリスマスローズ(2月中旬から3月上旬)
クリスマスの時期に咲くことからこの名がありますが、2月ごろにならないと、花の咲いているのを見たことがありません。下を向いて咲くので写真に撮るのが難しい花の代表格ではないでしょうか。花言葉は「追憶」としている図鑑もあれば「スキャンダル」と書いているものもあり、いろいろと大人の事情がありそうです。


セツブンソウ(1月下旬から2月中旬)
2月上旬、節分の時期に咲くことからこう呼ばれます。本州の関東地方より西を中心に石灰岩質の地帯に自生します。花仲間ガーデンに咲きます。遠方からも多くの方々が、この花を楽しみに来園されています。


見渡す限り、というほどではないですが、セツブンソウだけが群生して咲くエリアがあるので、花期にはそれなりに見ごたえがあります。

キバナセツブンソウセツブンソウの仲間で、黄色い花を咲かせます。セツブンソウの見ごろよりやや遅れて咲き始めます。エランティスというカタカナ名前もありますが、その花言葉は「人間嫌い」。騒がずそっと見守ってあげてください。


ネコヤナギ(2月中旬)
ネコヤナギ(猫柳)はヤナギ科の落葉低木で、水辺に好んで生えます。花仲間ガーデンの池の端で咲いています。この植物は、花の咲く前に、手触りのいいモコモコした毛を生やした花穂(穂のようにつける花)をつけるのが一番の特色です。これが猫のしっぽのように可愛らしく見えることが名前の由来です。だんだんこの「しっぽ」が大きくなると、毛の間から胞子のような花序が出てきます。先端には黄色い花粉がついており、ちょっとなんとも言えない造形をしています。
発芽から猫のしっぽが登場し花が咲くまでを順に掲載します。

第一段階 産毛のような毛に覆われた芽(2024年1月30日撮影、以下四枚目まで2024年)。

第二段階 毛が白く見える。芽自体もまだ小さい(2月14日)。

第三段階 毛が銀白色のようになり、毛の奥にある芽が赤っぽく透けて見える。芽を覆っていたカバーのような先端部分が次第に脱げるように上に向かって外れていく(2月19日)。

第四段階 カバーも取れて、一人前?のネコヤナギ状態。毛はとてもふわふわしていて思わず触ってしまう。水を弾くので、雨の後は毛先に大小の雨粒がそのままこぼれず乗っていてとてもきれい(2月20日)

最終段階。モコモコの毛の隙間から雄花と雌花が伸びてくる。この状態ではとてもネコという感じはしない。(2022年3月10日撮影)
ミニアイリス(2月中旬から3月上旬ごろ)


アイリスは300種類もある宿根草で、ほとんどは春から夏に咲きますが、晩秋から晩冬の寒い時期に咲くものもあります。アイリスは根茎性と球根性の二つの性質に分かれ、ここで紹介する球根性のミニアイリスは、学名ではレティキュラータという種類です。この種類は春の草花より一足早く、2月の後半に姿を見せます。3月にかけて次々に咲き、夏場は休眠しているそうです。
シナマンサク(2月中旬から3月上旬)
人の名前見たいな樹名ですが、春の野山に「まず咲く」→「マンズサク」が由来などと言われています。春のさきがけの樹木なのでしょう。桜の咲くちょっと前に、ちぢれた黄色い花を大量に咲かせます。遠くから見ると、黄色い雲がぼんやりと浮かんでいるようで、意外ときれいなのです。


見れば見るほど、何ともユニークな花の形です。

遠景

青空を背景に見ると、なかなか引き立つ花です。


更新日:2024年06月27日