王国植物だより(春)
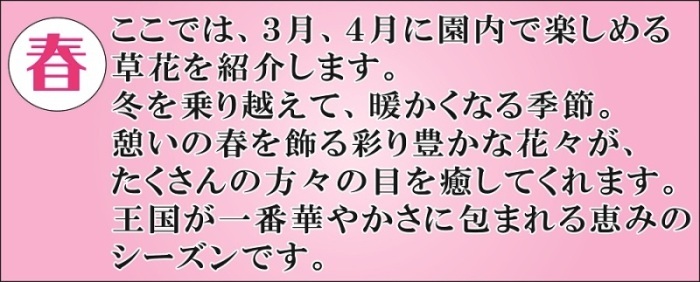
注:種目の後の月の表示は見ごろの時期を表しています。
なお、原則としてそれぞれの草花の写真を撮影した時期を開花期(見ごろの時期)と見なしています。植物図鑑等で開花期として表記されている時期と異同がある場合や、撮影した時期以前から既に開花している場合もあります。また、その年によって開花状況が異なることや、開花しない場合もありますので、あくまでも参考としてご覧ください。
雪割草(ミスミソウ)(3月上旬)
冬から春へと移り変わる時期に、雪を押しのけるようにして咲く花を「雪割草」と総称するようで、フクジュソウも雪割草と呼ばれるそうです。ここでその名で紹介するのは、「ミスミソウ」です。緑の王国のある櫛挽周辺ではあまり降雪はありませんが、最初は地を這うように伸びて蕾をつけていた茎が、次第に天を向き立ち上がるようにして花を咲かせる姿は、可憐ながらも「雪を割って」成長していく逞しさを感じさせます。王国では一重咲きがほとんどですが、花弁の数が多い多弁咲きや八重咲き、雄しべの形がユニークな日輪咲きなど、咲き姿にもいろいろとバリエーションがあるそうです。


年に何度か雪が降った日には文字通り「雪割草」になります。



タイリンミツマタ・ミツマタ(3月上旬)
タイリンミツマタもミツマタもヒーリングガーデンにあります。古くから日本にある植物で、原産地は中国の高山地帯です。かつては和紙の素材として使われました。花の形は同じですが、タイリンミツマタの方が花は大きく、枝も太く、咲く時期も早いです(ミツマタはすべてその逆)。12月ごろには、シャワーヘッドを思わせる面白い形のつぼみをつけています。外側から内側に向けて徐々に花が開いていきます。

タイリンミツマタ

タイリンミツマタのつぼみ

タイリンミツマタ

ミツマタ

ミツマタ
シラー(3月上旬)
シラーはユリ科ツルボ属の多年草です。ヨーロッパからアジアの草地や森林地帯に広く分布します。およそ90種類あり、鈴に似た形の下向きの花をつけます(ベル咲き)。緑の王国では春先の2月下旬から3月ごろに、主に下の2種が咲いているのが見られます。

シラー シベリカ
きれいな青い花をつけます。咲き始めは地についていますが、次第に茎は長くなります。ウクライナ、ジョージア、アゼルバイジャンが原産地です。

シラー カンパニュラータ(スパニッシュ ブルーベル)
シラーの近縁種ですが、分類学上は違うそうです(学名はハイアシンソイデス・ヒスパニカ)。たくましい性質で、木陰でも60cmほどの大きさに育ち、群生します。2cmほどの薄紫色の花を縦に15個ほどつけます。スパニッシュ ブルーベルは英語名で、この呼び名でもよく知られています。
プーシキニア(プシュキニア)(3月上旬)

まだ他に咲く花のほとんどない春先に花仲間ガーデンに咲きます。地面の中から出てきたツノのように小さな花ですが、次第に広がり大きくなります。高さはあまり変わりません。原産地はコーカサス地方。花弁に藍色の縞模様ができるのが特色です。ただ花仲間ガーデンに植栽されているものは、近縁種のチオノドクサと混在している可能性があるそうで、そのためか、花弁の縞模様は薄くてはっきり見えません。
リュウキンカ(3月上旬)
リュウキンカは沼地や湿地を好む多年草で、春先に咲きます。花弁に見えるのは「がく」の部分で、花弁はありません。茎が直立し、金色(もちろん純金ではありませんが)の花を咲かせることから、「立金花」と呼ばれます。陽光を浴びてピカピカ光る花弁状の「がく」はとてもきれいです。エナメル質にも見えます。花仲間ガーデンやラクウショウの森の水辺に咲いています。


レンギョウ(3月上旬)

春先に、星のような黄色い花をたくさんつけるレンギョウ。原産地の中国では「黄寿丹」、韓国では「ケナリ」と呼ばれ、それぞれ長く愛されています。日本でも古来より親しまれており、薬草としての歴史も長く持ちます。少なくとも10世紀の書物には、薬草としての言及があるとか。(解熱剤、皮膚病の治療に実を使用したそうです。) 中国や朝鮮半島でも親しまれてきたのは、「シナレンギョウ」、「チョウセンレンギョウ」という種類があることからもわかります。下の写真はシナレンギョウで、枝がまっすぐに伸び、花が俯き加減に咲くのが特徴です。チョウセンレンギョウは外側へ大きく展開するように咲き、幹や枝が次第に弓のように弧を描き始めるのが特徴です。まだ花の少ない時期に、黄金の固まりのようなレンギョウが陽光に輝く姿は、なかなか心を揺さぶるものがあります。

スモークツリーガーデンのチョウセンレンギョウ。周囲の枯れた情景の中でよく目立っています。

こちらはローズガーデンのフェンスに絡みついているレンギョウです。

1枚目の写真と同じシナレンギョウ。カエデ通りの梅園の向かい側に咲きます。直立してすっと伸びていく姿がよくわかります。

スモークツリーガーデンのチョウセンレンギョウ。自由奔放に花をびっしりつけた枝が広がっていきます。
ダンコウバイ(3月上旬)

ダンコウバイ(壇香梅)は関東地方より西、四国から九州の山地に多く自生し、庭木としてもよく使われます。枝にはビャクダンのような香りがあり、楊枝の材料としてもお馴染みだそうです。「梅」の字が入っていますが、梅とは関係なく、クスノキ科に属します。
ヒヤシンス(3月中旬から4月)
単色の独特な形の花がどこか生々しいたたずまいのヒヤシンスです。ヒーリングガーデンと花仲間ガーデンで見ることができます。30cmほどの高さに育ち、青と赤が咲きます。日本には江戸時代には渡来しており、「風信子」の字で親しまれてきました。有毒です。



沈丁花(3月中旬)
松任谷由実の「春よ、こい」にも登場する沈丁花(ジンチョウゲ)は、春のさきがけの花として多くの世代になじみ深い花でしょう。庭木や公園などに植えられる木でもあります。沈丁花といえばその薫り高いにおいがまず思い浮かびますが、鉛筆を集めたような蕾が一つ一つほどかれて、星形の花が顔を出すさまにも初春の趣があります。香りのする花々で訪れた人々に癒しを与えようとのコンセプトで2015年に作庭され、環境省の第10回みどり香るまちづくり企画コンテストで環境大臣賞を受賞した「「Healing Felling Garden 癒しの庭(通称:ヒーリングガーデン)」には白花の沈丁花があります。また2021年に同じコンテストに関連して受賞した「みどり香るまち大賞」の副賞として贈呈された紅花の沈丁花も、園内に植えられています。


沈丁花(咲き始め)

白花の沈丁花(ヒーリングガーデン) 香りの花々で訪れた人を癒すというコンセプトの「ヒーリングガーデン」に、香りの花の一種として植えられています。
梅園(3月の様子)
ふかや緑の王国は、その前身が埼玉県農林総合研究センター園芸研究所であったことから、花木の種類が豊富で、梅はおよそ100種類が植えられています。梅にそんなにたくさん種類があることがまず驚きですが、確かに色や形、咲く時期など、注意深く見ると皆違っているのです。 早いものは「冬」の項目で紹介した通り1月から咲き始めますが、ようやく全ての梅が咲き揃うのは2月下旬から3月上旬。3月中旬に入ってしまうと、もう終わりです。
冬の部でも言及しましたが、近年バラ科の梅や桜を中心にクビアカツヤカミキリの侵食が拡大しており、梅園の梅も被害が出ています。枯死している梅も散見されており、伐採や補植の対応をしています。







イカリソウ(3月中旬)


キバナイカリソウ
花の形が船の錨に似ているのでこの名で呼ばれます。淡い紫がかった色が大半ですが、園芸種では黄花も見られます。若葉や花を食用にします。薬草としても様々な効果があり、有名です。
桜(3月中旬から4月)
梅もたくさん種類がありますが、桜も様々なものが見られます。ソメイヨシノや、ちょっと遅めの八重桜、紅色が目に鮮やかなヒカンザクラ、中には秋から冬にかけて咲いてしまういわゆる「十月桜」もあります。 樹齢数十年であろうと思われる大樹ばかりですが、王国ひろばには、緑の王国建国10周年記念として、2018年に桜の若木を植樹しました。まだひょろひょろの目立たない木ですが、毎年しっかりと花をつけています。こちらも注目してあげてください。
梅と同じく、桜もクビアカツヤカミキリの被害を受けており、枯れ木も増えています。伐採した木も多く、園内の桜の本数はここ数年で減少しています。


通用門側駐車場裏に咲くソメイヨシノ。

山野草ガーデン池のほとりに咲くソメイヨシノ

ヒカンザクラ(山野草ガーデン)

葉桜
カタクリ(3月下旬)
カタクリといえば片栗粉がすぐ連想されますが、これはラッキョウに似た根茎を磨り潰して作ったものです。花のカタクリは3月下旬ごろに、まだら模様のある葉の間から茎が伸び、先端に紫色の花を咲かせます。カタクリの花は花弁と「がく」の区別がつかない花被片(かひへん)というものですが、これが次第に後ろに反り返って茎の先端をくるむようになるのが面白い点です。山野草ガーデンにあります。



スノーフレーク(3月下旬)
スノーフレークは、「オオマツユキソウ」「ギンランスイセン」の名もあるヒガンバナ科の球根植物です。3月下旬頃から咲いているのが見られます。スズランに似ていますが、花弁の先に緑色の斑点がつくのが特徴的です。花仲間ガーデンの池の周囲、またヒーリングガーデンでもたくさん咲いています。


コブシとモクレン(3月中旬から下旬)
同じ時期に咲く形の似た花なので間違いやすいかもしれませんが、コブシの方がモクレンより花びらが薄く、そしてコブシは花が咲く時にはもう葉が出ています。(モクレンは花が終わってから葉が出る種類が多いそうです)葉の形で見分けるなら、一般的にコブシの葉の方がモクレンよりも丸みがあるようです。 コブシは蕾の形が子供の握りこぶしに似ていることからこの名がついたと言われます。昔はコブシが咲くと農耕の準備や種まきの目安にしたようで、「田打ち桜」、「種まき桜」との異名でも知られています。コブシの花を見てどっこいしょと腰を上げるお百姓さんの姿が見えるようです。 モクレンは中国原産で、なんと1億年前の化石も見つかっているほど古くからある樹木です。欧米では「マグノリア」の名で愛され、世界的に親しまれる春を代表する木と言っていいでしょう。あたかも燈火を捧げ持つように天を向いて咲く花で、中がどうなっているのか、ほとんどわかりません。花弁が大きく、色も美しく、樹高があってひと際目立つため、長く親しまれているのでしょう。 緑の王国ではヒーリングガーデンや山野草ガーデンでハクモクレンを、花仲間ガーデンで桃色のサラサモクレンと紫色のシモクレンを、王国通りと花仲間ガーデンでコブシを見ることができます。 (下の写真はヒーリングガーデンのハクモクレン)


ハクモクレンの花

シモクレン(花仲間ガーデン)

サラサモクレン(花仲間ガーデン)

ヒーリングガーデンのハクモクレン

ヒーリングガーデンのハクモクレン
二本並んで咲きます。咲いている期間はあまり長くないですが、とてもきれいです。

山野草ガーデンのハクモクレン

モクレン「サヨナラ」の全体写真(花仲間ガーデン)
モクレンは125種類あるそうですが、これは「サヨナラ」という種類です。学名もMagnolia 'Sayonara'といい、由来はよくわかりませんが、日本語の別れの意味が込められているのは明らかです。このふかや緑の王国の前身、埼玉県農林総合研究センター園芸研究所が閉所となるとき、最後の職員のかたがたが記念に植樹していったと伝えられています。4月初頭に花弁の底がやや紫がかった、12cmほどの乳白色の花をつけます。

コブシ(花仲間ガーデン) モクレンより花弁が薄手で、花と葉が両方見られます。 3月半ばの王国通り。コブシとモクレンが両方見られます。

モクレン「バルカン」(ヒーリングガーデン)

コブシ(花仲間ガーデン) 花弁に縮れがあります。
バイモ(3月下旬)
漢字では「貝母」と書きます。地中の鱗茎が貝殻を合わせたような形をしているのが由来とのことです。花の内側に網目模様ができることから「アミガサユリ」とも言います。あまり目立たない花ですが高さ50センチから60センチにも成長します。薬草としても活用され、鱗茎は咳止め薬や解熱薬にもなります。花仲間ガーデン、メディカルガーデンで見ることができます。



バイモの花弁の内側 なるほど網状の模様が入っています。
アネモネ(4月上旬)
アネモネは地下茎や球根を持つ宿根草なので毎年いつの間にか咲いています。目のようにも見える中央の突き出したような雄しべが特徴的です。色も様々で、種類も豊富(約120種)。「ジャパニーズアネモネ」と通称されるシュウメイギク(秋の部に記載)のように秋咲きのアネモネもありますが、ここで取り上げるのは4月上旬に咲く種類です。主に花仲間ガーデンとフローラガーデンで見られます。

ミヤコワスレ(4月上旬から5月)


キク科の多年草で、アズマギクなどの名前もあります。スッと伸びた茎に白や青紫の花をつけます。山地や水辺を好むようで、春先にたくさん咲きます。印象的なこの名前は、承久の乱(1221年)で佐渡に流刑となった順徳天皇(後鳥羽天皇の息子)がこの花を見て、都にいたころの華やかな思い出も忘れさせてくれる花だ、と感じたことが命名の由来とされています。それほど特徴的な花というわけではありませんが、そのありふれた佇まいに安らぎを覚えさせる花です。
ラショウモンカズラ(4月上旬)

山地の湿地や川沿いを好みます。高さは20センチから30センチほどに成長します。一度聞いたらなかなか忘れられないこの名前は、「羅生門の鬼」で源頼光の四天王と言われた渡辺綱が切り落とした鬼の腕にちなんでつけられたとされます。私は会ったことがないのでよく分かりませんが、鬼の体は青く描かれたりするし、唇を突き出したような形の小花が一列に並んでいる感じが、鬼のゴツゴツした腕の様子を想起させたりするので、こんな名前がついたのでしょうか。花仲間ガーデンに広がって咲いています。
サクラソウ(4月上旬から下旬)
ここで紹介するのは、いわゆる日本サクラソウであり、西洋サクラソウとして知られる種類はプリムラ(プリムローズ)と総称されます。日本サクラソウは育成が容易でない品種が多く、しかし改良や掛け合わせがしやすいことから、江戸時代より根強い人気を保っている花です。 4月も後半にさしかかる時期に、皺の寄った厚手の葉の中からすっと伸びた茎の先に、桜のような可愛らしい花を咲かせます。薄紅と白が主な色ですが、紅にも微妙な濃淡の差異があり、また花弁の形もよく見ると一本一本少しずつ違っています。山野草ガーデンとさくら草ガーデンで主に見られます。さくら草ガーデンは、ガーデン全体に広がって咲くのでなかなか見ごたえがあります。


ざっと見ただけでも、花弁に微妙な違いがあることがわかります。一つ一つ種類が違うようです。


ウラシマソウ(4月上旬)
ウラシマソウはサトイモ科の多年草です。山林や竹藪など湿ったところに生えます。緑の王国では花仲間ガーデンのクスノキの木陰にあります。サトイモ科の花は仏炎苞(ぶつえんほう)と呼ばれる花を包むひさしのようなものがついており、ウラシマソウにもそれが顕著に見られます。その仏炎苞からのびている紐状の部位を、浦島太郎が垂れている釣り糸になぞらえてこのような名前がついているそうです。言われてみるとそんなように見えなくもない、ユニークな植物です。

U字に紐が垂れる様は確かに釣り竿と釣り糸のように見えます。
リキュウバイ(4月上旬)
リキュウバイは中国由来のバラ科の落葉低木です。日本には明治時代に渡来し、茶花としてよく使われたことから千利休にちなんでこう呼ばれるそうです。さほど普及率が高くないためどこでも見られるというわけではないようですが、4月初めに白い花をたくさんつけて風に揺れている様子はとても見ごたえがあります。


ヤマブキ(4月上旬)
ヤマブキは日本と中国に分布する落葉低木です。黄色く大きな五弁花がよく目立ちます。高さは2メートルにもなります。ロックガーデンやサステナブルガーデンで見られます。

ヒトリシズカ(3月末から4月上旬)
あまりメジャーな花ばかり紹介していてもつまらないので、ちょっとここで知られざる(そうでもないかな)花を一つ。 センリョウ科に属する山野草のヒトリシズカです。源義経の悲恋のパートナーと言われる静御前に因んで名づけられています。「静御前のように優美な姿」などとまことしやかに書いている図鑑もあり、「会ったことあるんですか?」と突っ込みたくなりますが、ちょっと独特の存在感のある花です。 4月に差し掛かろうという頃、色艶がよく葉脈の彫りが深い葉の中からブラシのような形をした花が出てきます。これは雄しべで、花糸と呼ばれるものです。一本の中から一つしか花が咲かないため、「ヒトリシズカ」と呼ばれ、これの仲間で二つ以上花の咲くものを「フタリシズカ」と言います。(最もヒトリシズカでも二つ咲く場合もあります。)フタリシズカの方が花は遅く、5月頃に咲きます。


肩こりをほぐす健康器具にこんな形のものがあったような・・・?それにしても、一口に花と言っても実にいろいろな咲き方をするものだと感心してしまいます。
ヤマシャクヤク(4月上旬)
ヤマシャクヤクは高さ40~50センチになる多年草で、茎の先に白い花を一つ上向きにつけます。咲き始めはシュークリームのような形に見え、花弁は完全に開ききることなく、次第に一枚、二枚と散っていきます。山地に生え、シャクヤクに似ていることが名前の由来です。ヤマシャクヤクの仲間で紅花をつけるベニバナヤマシャクヤクも5月下旬から6月に山野草ガーデンで見ることができます。


ヤマシャクヤクのつぼみ

咲き始めのヤマシャクヤク

ベニバナヤマシャクヤク

八重咲のヤマシャクヤク
クロフネツツジ(4月上旬から中旬)
花仲間ガーデンのサラサモクレンの裏にあるピンクの花を咲かせる木がクロフネツツジです。 何が黒船かと言えば、黒船(外国船)によって海外からもたらされたことに因んでいます。とは言え、史上有名なペリーの黒船ではなく、17世紀半ばに渡来したと言われています。中国から朝鮮半島に自生するらしく、黒船の出所もそのあたりなのでしょうか。 なんといってもこの花は、色彩といい花の形といい大きさといい咲く量といい申し分なく豊かで美しく、優雅で気品と華を感じさせ、「ツツジの女王」と呼ばれるのも頷けます。あまり背が高くないので咲くまでは目立ちませんが、空間の裂け目からあふれ出すかのように満開に咲く光景には感動します。


ハナミズキ通りから花仲間ガーデンを抜けスモークツリーガーデンへ至る小道の途中にあります。

チューリップ(4月中旬から下旬)
どの花見てもきれいなチューリップ。その原産地は、一説には中国・天山山脈とされています。昔トルコ軍がここまで攻めてきた時、山の中に咲く色とりどりの花に感激し、祖国に持ち帰り愛好家が増えました。冷酷無残な人が多い歴代のスルタン(皇帝)の中にも、自らチューリップを栽培し作庭にいそしむ人が多かったそうです。ヨーロッパに移入するのはその後。トルコ人の巻くターバンに因んで、「チューリップ」という名で呼ばれるようになり、交配による微妙な斑の違いがもてはやされるようになりました。 殊に17世紀中期のオランダでは、いわゆるバブル経済を引き起こしたとされるほど投機の対象となり、価値が上がりました。ある商人が残したわずか30株ほどのチューリップで、その遺児6人が一生涯ラクに暮らせるだけの金額になったとか・・・。全く嘘のような話です。 しかし人間の迷いには関係なく、花は花で毎年しっかり咲いています。牧場ガーデン、ヒーリングガーデン、花仲間ガーデン、フローラガーデンなど、どこを見てもチューリップ!という時期も。色も種類も豊富で、原種のものも咲いています。 (下はサンクンガーデン)


牧場ガーデン

フローラガーデン

ヒーリングガーデン ここには原種のものも植えられています。

花仲間ガーデン

フローラガーデン

王国通り突き当たりの植え込みのチューリップ
ハナミズキ(4月中旬から下旬)
1912年、当時の尾崎行雄・東京市長が、日米友好のためにアメリカへソメイヨシノを贈り、その返礼として1915年にアメリカからやってきたのが、どうやらハナミズキのルーツであるそうです。尾崎が贈ったソメイヨシノは虫害が発生したため全て焼却されてしまいましたが、アメリカ側から「紅花苗10本と白花苗40本」が贈られてきた中の一部は、現在も日比谷公園に残存しているそうです。およそ100年で、今や日本中に広まったハナミズキは、海を越えた友情の証とも言えるでしょうか。 日本名は「アメリカヤマボウシ」と言い、言われてみると葉の上に乗っかるように咲いている花の姿はヤマボウシを彷彿とさせます。ヤマボウシのように、秋になると赤い実をつけます。 緑の王国の正門を入るとすぐ目の前を続く道が「ハナミズキ通り」で、道に沿って赤と白のハナミズキが植えられています。カメラを向ける人も多く、緑の王国の春の象徴と言える大事な樹木です。





ハンカチノキ(4月中旬から下旬)
苞と呼ばれる部分をハンカチに見立てて、このような名で呼ばれます。中国の高地に自生するそうですが、日本でも化石が見つかっているらしく、かつては日本国内でも育っていたようです。しかし今となっては馴染みの薄い木ではないでしょうか。木全体が葉をつけたなと思うと、その隙間からチラチラと「ハンカチ」が揺れているのが見え、咲いていることに気づきます。一気に咲くとなかなかきれいですが、やがて「ハンカチ」は虫に食べられたり縮んだりして見えなくなってしまいます。



2024年はびっくりするほど花がつきました。まるで実に保護用の紙袋をつけたリンゴの木のようです。

ヤグルマソウ(4月下旬から)



ヤグルマソウは五つに裂けた大きな葉が特徴的で、これを鯉のぼりの矢車に見立ててこう呼ばれています。地方によって様々な呼び方があり、この辺りだと秩父地方では「ゴハ(五葉}」と言われるそうです。山野草ガーデンの池のほとりで咲いています。
なお、紫やピンクの紙細工のような小さな花を咲かせる植物も「ヤグルマソウ」と呼ばれますが、あちらの花は正式には「ヤグルマギク」なので、注意が必要です。
ハクウンボク(4月中旬)
ハクウンボクは漢字では「白雲木」と書きます。白い花が、雲がたゆたっているように見えるためです。4月半ばくらいに釣り鐘型の小さな花を並んでつけますが、咲いている期間は短く10日ほどで散ってしまいます。

オダマキ(4月下旬)
オダマキは春先にたくさん群れて咲く花です。花色が豊富で様々な場所に咲いているのを楽しめます。艶のある複雑な形をした美しい花が特徴的で、気品のあるたたずまいです。スモークツリーガーデン、ロックガーデン、山野草ガーデンで見ることができます。




タイツリソウ(4月下旬)
タイツリソウという名前の通り、鯛を釣り上げたような形に見えることからこう呼ばれます。仏具の「華鬘(けまん)」に似ることから「ケマンソウ」とも言いますが、前者の名前のほうがインパクトがあります。江戸時代に中国から伝わり、観賞用として楽しまれてきました、高さ60センチにもなります。赤花が一般的ですが、白花も咲いています。どちらも花仲間ガーデンで見ることができます。


赤花のタイツリソウ

夕方のタイツリソウ


更新日:2024年07月10日